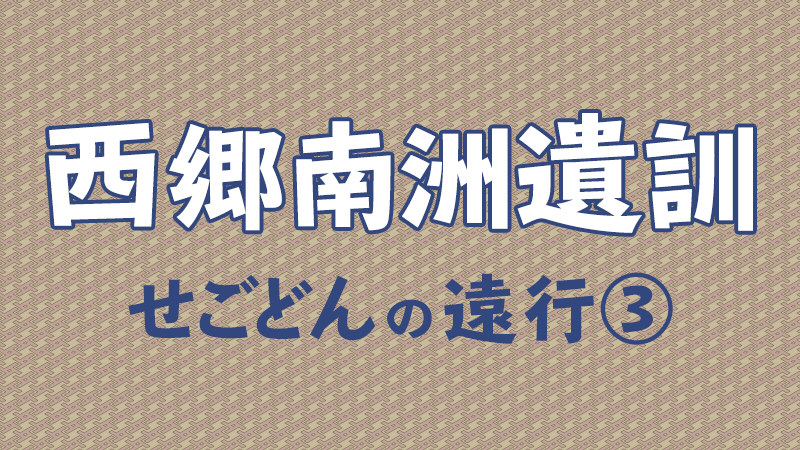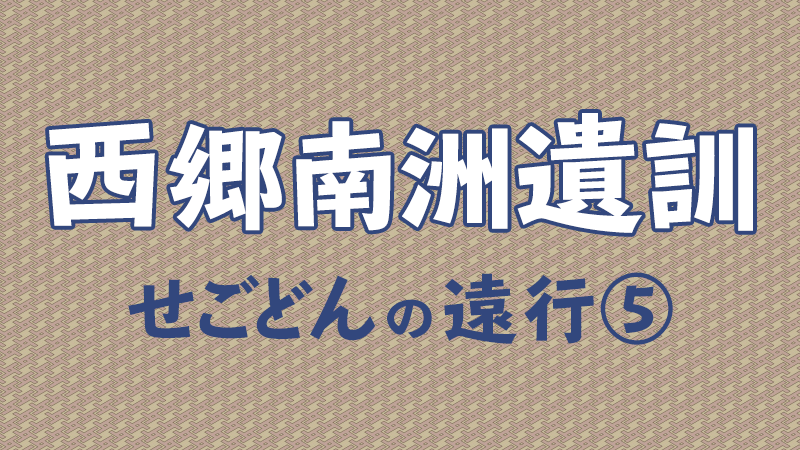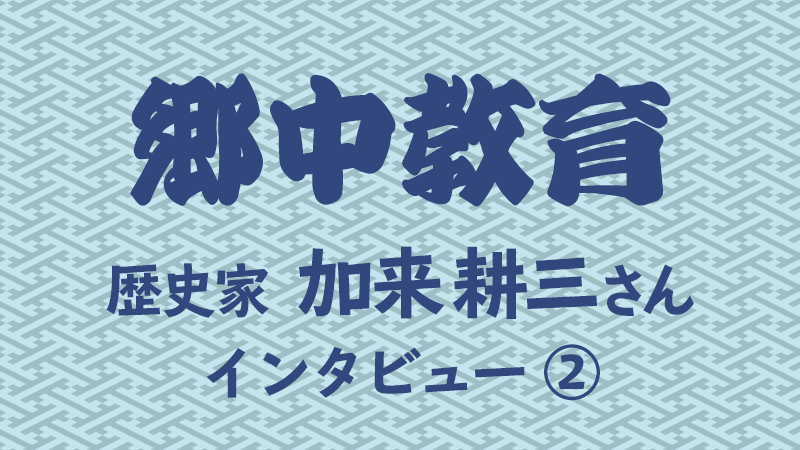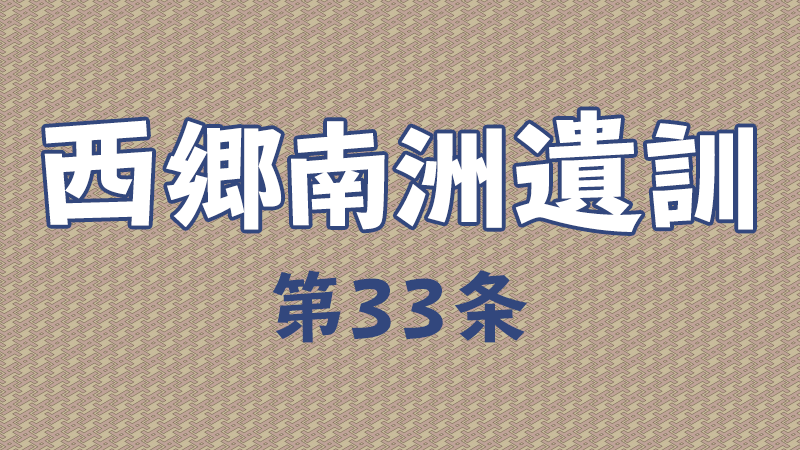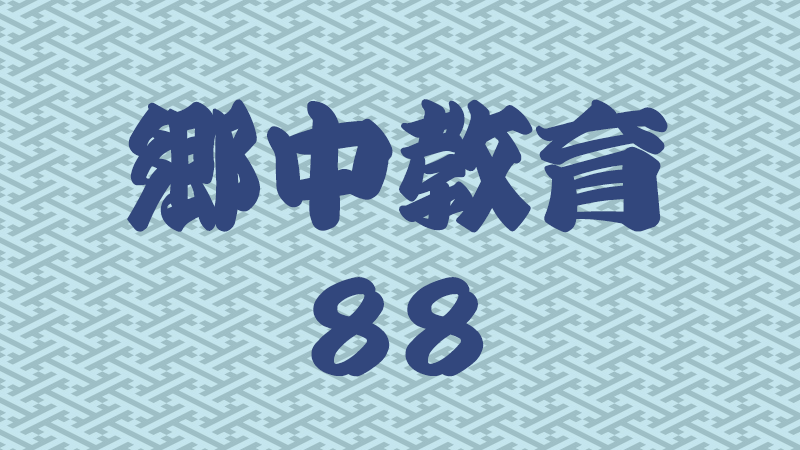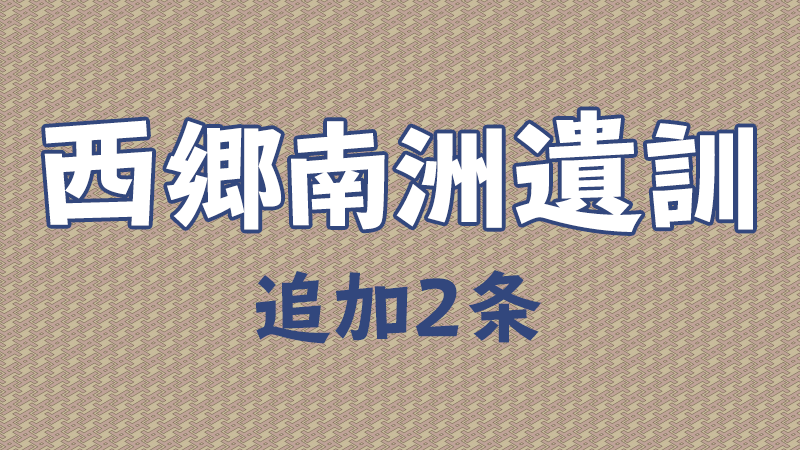今週は、先日行われた「せごどんの遠行」の模様をお送りしています。
今日は、南洲翁洞窟の説明からお聞き下さい。

(ボランティアガイドさん)「今から141年前、1877年、9月24日でした。
亡くなる5日前までこちらの洞窟に立てこもっておられました。
9月24日というとね、今日はいいお天気ですけれど、その頃は雨が降り続いていたんだそうです。
9月に雨が降ると何が発生するかわかりますか?」
(子供たち)「土砂崩れ、台風、虫・・・」
(ガイドさん)「蚊がいっぱいいたんです。西郷さんは蚊に刺されながら、ここに5日間過ごしておられたんですよ・・・。」
各ポイントでボランティアの皆さんがこういう説明もしてくださるんですね。
聞いていたのは草牟田小学校の子供たちでした。引率されていた木下先生にお話を伺いました。
(木下先生)「今日は草牟田小学校のあいご会で、せごどんの遠行に参加しています。
200人以上、全学年まんべんなく来ていると思います。高学年の子供たちのほうが比較的多いと思います。
子どもたちが普段はあんまり自分たちの住んでるところに対して、あまりたぶん城山の近くとか意識してないと思うんですが、歴史のことに対して誇りを持ったり、歴史を身近に感じたり、ふるさとに誇りを感じたり、そういう意識はせごどんの遠行を通して変わってきていると思います。
知らない逸話がすごく所々で聞かれて、自分もうれしいですし、そういうところに勤務できてることは誇りに思います。」
子どもたちにも感想を聞いてみました。
「いろんなせごどんのところへ行って、いろんなことを勉強できて、こんなところを回ったりするのがとっても楽しい。」
「歴史をよく知ることができました」
「毎年参加してても、毎年毎年いろいろわかる」

さあ、いよいよ明日はゴールの模様です。ゴールでは甲冑姿の方が、大きな声でみなさんを迎えてくれます。そして、せごどんの遠行を結ぶ一言もきかせてくれましたよ。
どんな一言か、明日もどうぞお楽しみに!