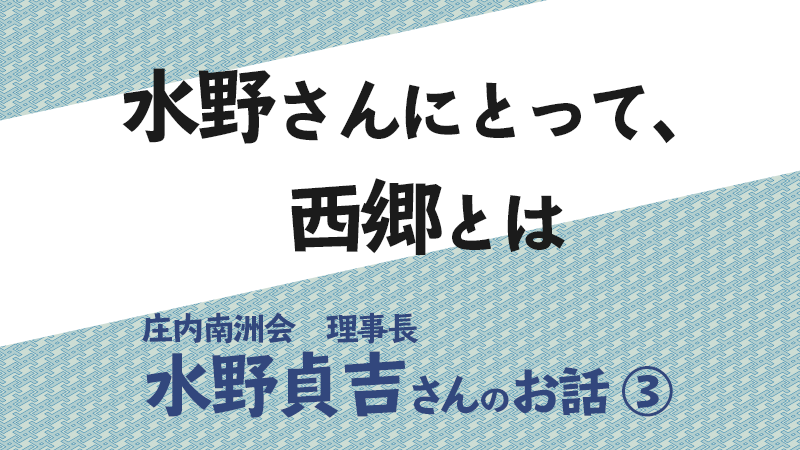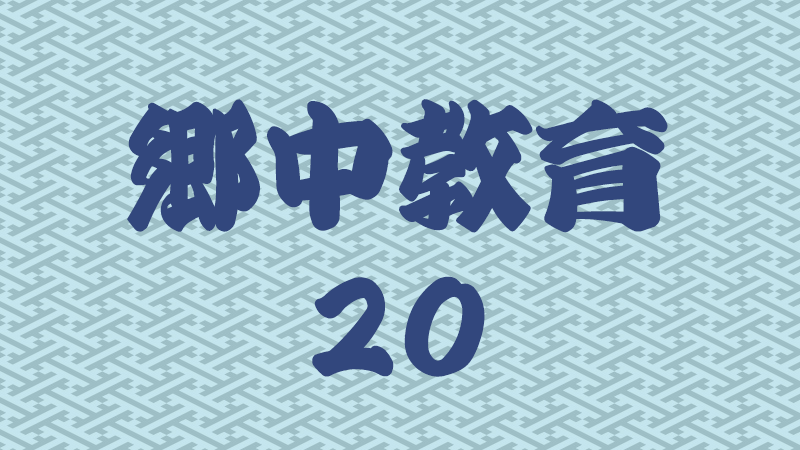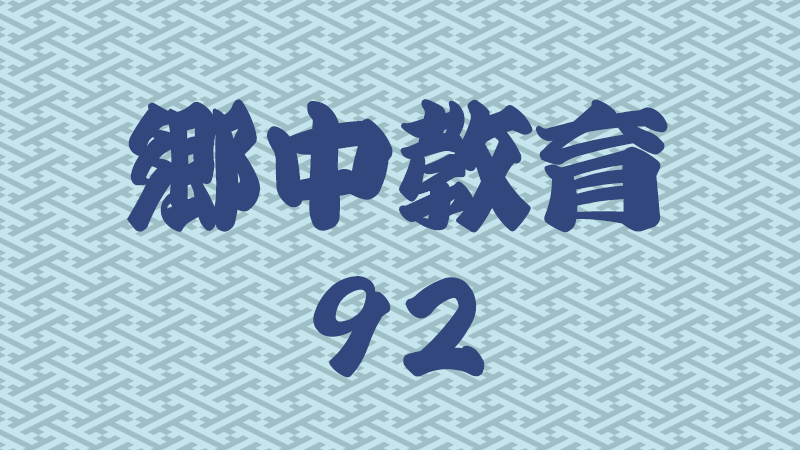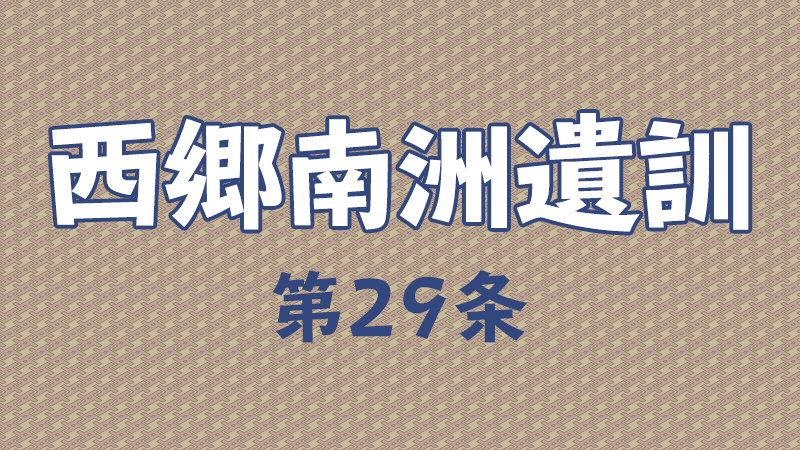今日ご紹介するのは、いろは歌の14番目の「か」の歌です。
まず、言葉の説明から…
- 「潮の ひるま」の「ひるま」は、潮が干(ひ)いて、干潮になるの「干(ひ)る」と、朝昼晩の「昼」とをかけてあります。
- 「波のよるこそ なおしずかなれ」の「よる」は、波が打ち寄せるの「寄る」と、朝昼晩の「夜」とをかけてあります。
次に「学問は あしたの潮の ひるまにも なみのよるこそ なほしずかなれ」の歌の意味です。
学問は、朝でも昼でも励まなければならないけれど、夜の方が特に静かで良いといった教えです。
日新斉は、幼い頃はヤンチャで、野山を駆け巡り、ひとときもジッとしていることはなかったようです。
ところが15歳で元服、今でいう成人式を迎えると、これまでの行動を深く反省し、自分が伊作家の家督を継ぐことに思いを強くし、机の前に座る機会が増えました。
昨日もご紹介したように、良い教師を得て、書物とニラメッコする時間が増えたと伝えられています。
例えば、学習時間を決め、その始まりの時間がくるとホラ貝を吹いて人々に知らせ、勉強中に人の訪問が無いよう工夫したり、旅行に行く際も書物を手から離すことがなかったようです。
『元より自然に備わりたる聡明の美質 年歯の進むに従いて愈々その光輝を放つ』と古文書は記しています。
日新斉は、これまでの経験から、このいろは歌の「か」を作ったのでしょう。
この歌 あなたの明日のお役に立てれば幸いです。
では、今日も鹿児島のこの言葉でお別れです。また明日。毎日ごわんそ!