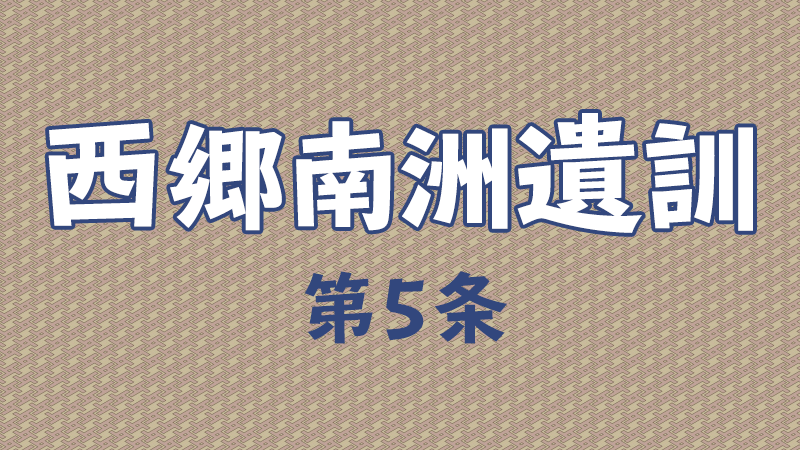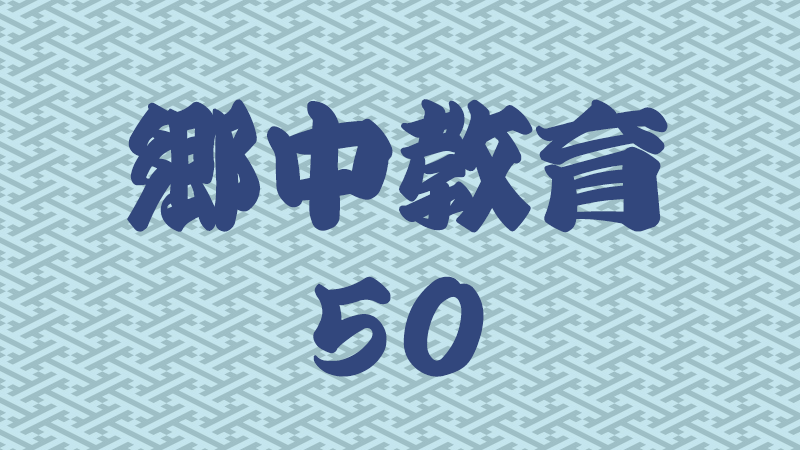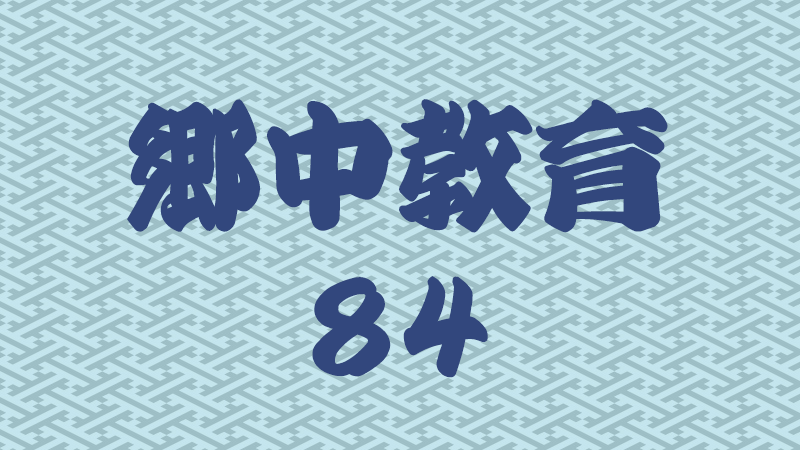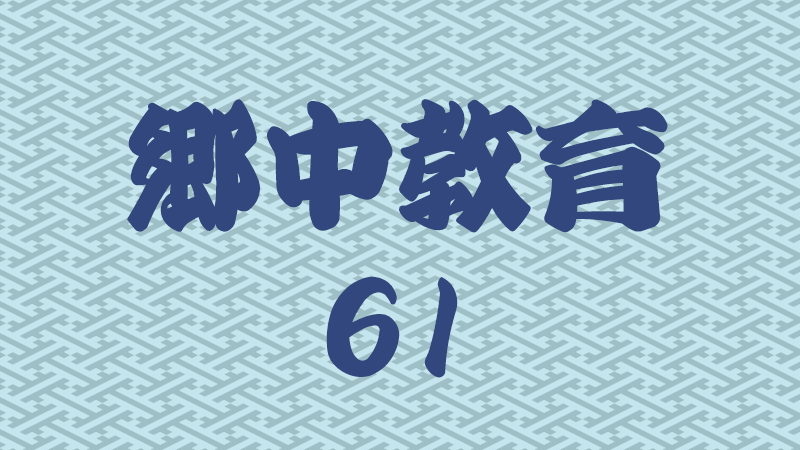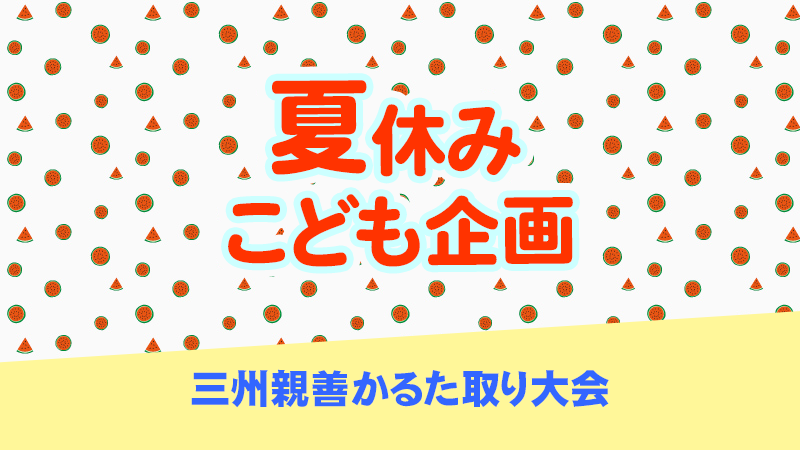今週から、島津日新斉が人生訓を説いた“いろは歌”を一首ずつご紹介していきます。最初は「い」からご紹介します。
「“いろは歌”は、島津日新斉が創ったもの」と思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
事実、その通りなのですが、番組では「菩薩日新公」として紹介して参りたいと思います。
そのわけは、彼が七才のとき、海蔵院という寺に入り、頼増和尚から厳しい教訓を受け、その中でいろは歌の基礎となる人の倫を学んだこと、そして、日新斉の法名を“梅岳常潤在家菩薩”と呼ぶため、「菩薩日新公いろは歌」としてご紹介します。
改めて、歌の意味です。
始めの“古の道”の意味は、聖人、即ち、高い学識、人徳や深い信仰心をもっている理想的な人。そして賢人は賢い人。つまり、
聖人や賢人が教えて下さった人の倫を何回聞いても、また「そんな倫、良く理解しているぞ」と、どんなに自慢しても、その教えを我が行いとしなければ、つまり実践してみなければ何にもならない…訓を実践するのが大切なのだ
要するに“不言実行”の教えなのです。
いろは歌が創られたのは、16世紀。およそ480年前、室町時代の末 天文8年から14年までの間と推測されます。
ちなみに天文12年8月 ポルトガル船によって種子島に火縄銃が持ち込まれています。
この歌、あなたの明日のお役に立てれば幸いです。
それでは、また明日。毎日ごわんそ!