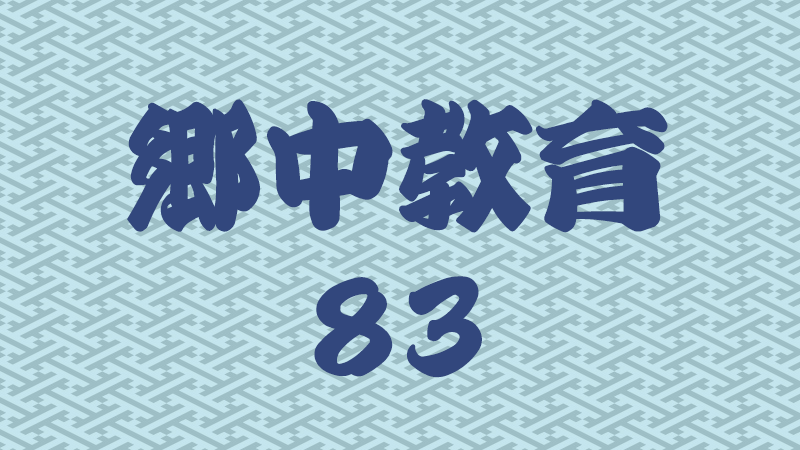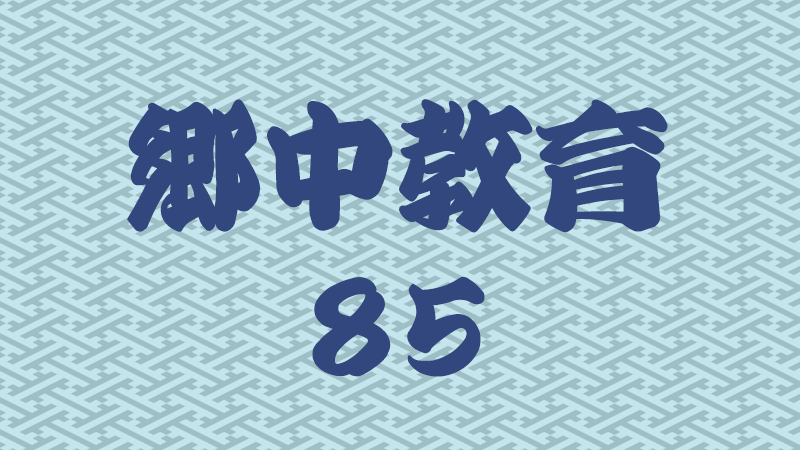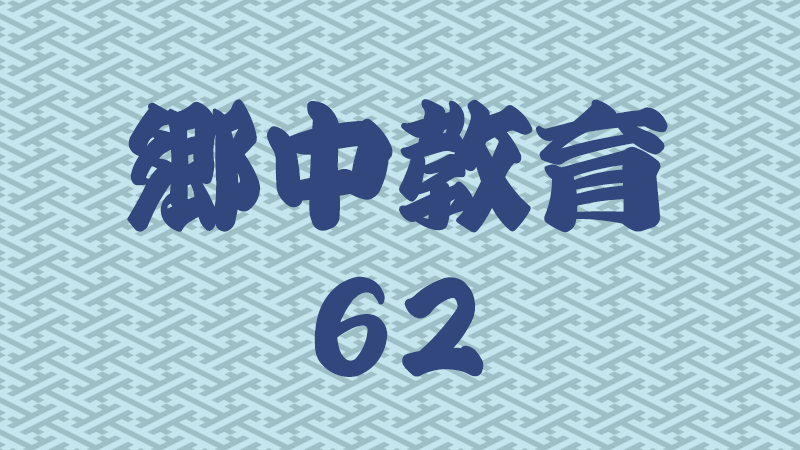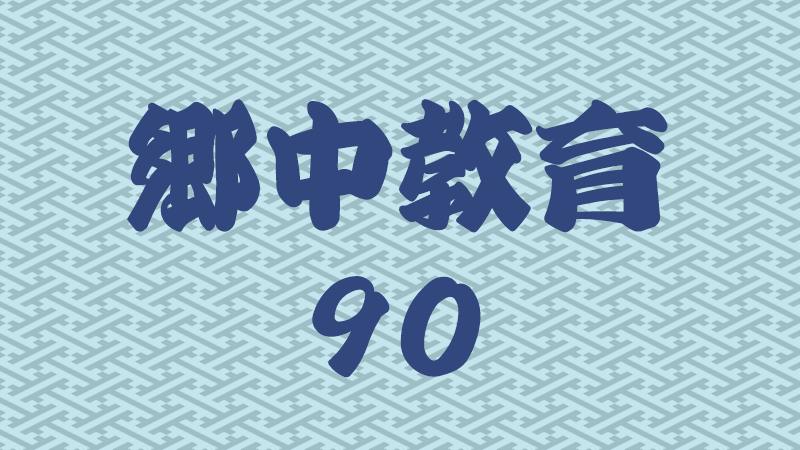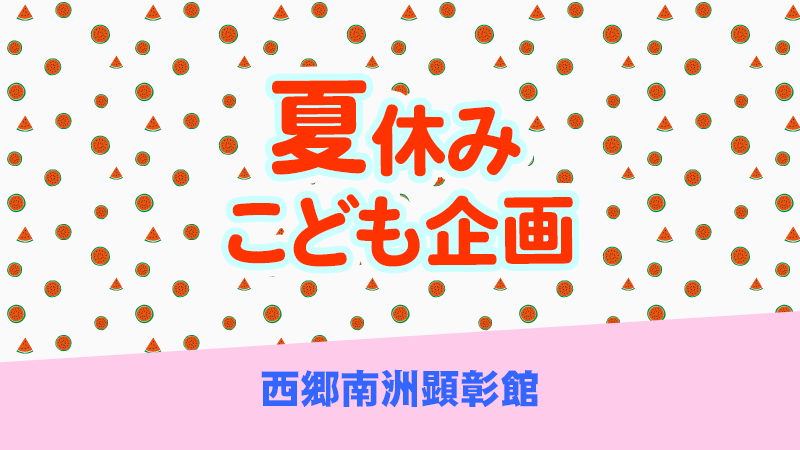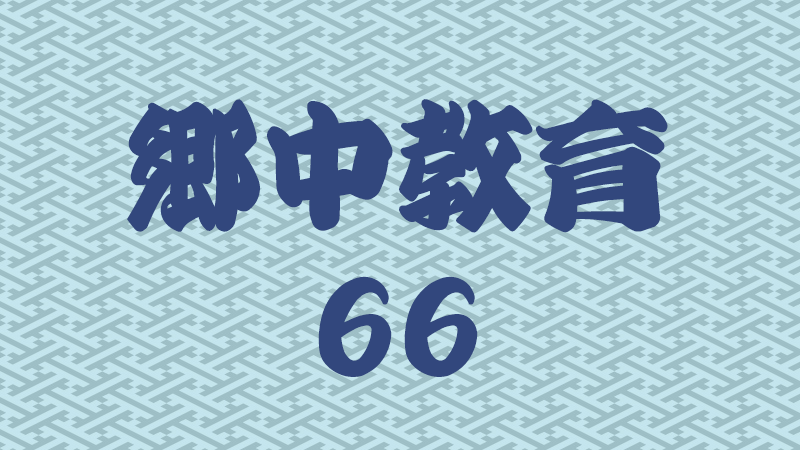明治維新から150年の今年、維新の力を生んだ「薩摩の教え」を改めて皆さんと共に学ぶこの番組。
昨日は、郷中教育で行われていた「詮議」についてお伝えしました。
たとえば、「盗んだお金を友達がくれるという。あなたはどうする?」という問いには、なんと答えたらよいでしょう?
その時の状況、自分の気持ち、相手の反応などをリアルにイメージする想像力と、とっさの判断を下す決断力が求められますね。頭脳の瞬発力は一朝一夕に身につくものではなく、繰り返しの訓練がものを言うように思います。
詮議教育は、戦国時代頃までは日本各地に存在したとも言われています。
江戸時代以前、文字の読み書きができるのはごく一部の人たちであったため、武士は一般的に、戦の成功例や失敗例などを聞き伝えることによって学び、議論しながら実践的スキルを身につけていたのです。江戸時代に入ると、文字による学問が普及しましたが、薩摩には、伝統的な教育スタイルが受け継がれました。当時、薩摩では、文字を読み書きできる人の割合、識字率が低かったという事情も関係していたそうです。
海外には、意見を闘わせるディベートという討論の方法もありますが、「詮議とディベートとは別物」と、加治木・精矛神社の宮司を務める加治木島津家第13代当主・島津義秀さんは言われます。
「日本人はそうじゃない。相手をまず尊重し、というのが入る。ちゃんと相手の意見を聞いて、自分の意見を言って、でも、どうなんだろうか、真理はどこにあるか、というのが目的で、相手を打ち負かすのが目的ではないんです」
いま教育現場では、アクティブラーニングという主体的な学習を取り入れる動きが進んでいますが、詮議教育は、より実践的なアクティブラーニングと言えるのかもしれませんね。
それでは、明日も、郷中教育の学びについてお伝えします。