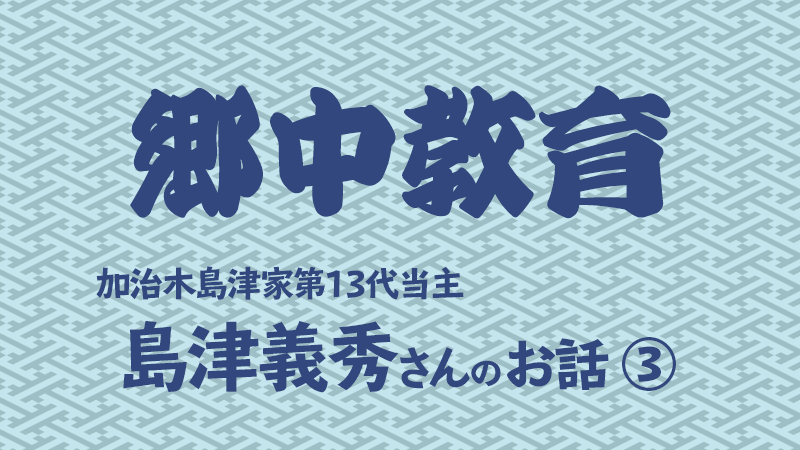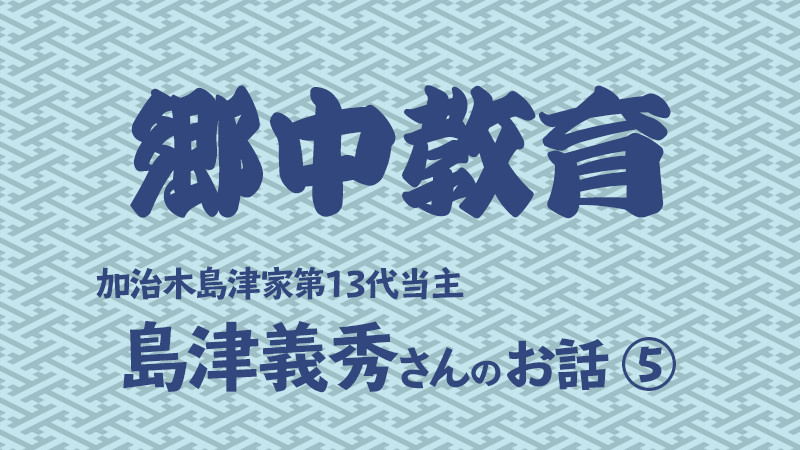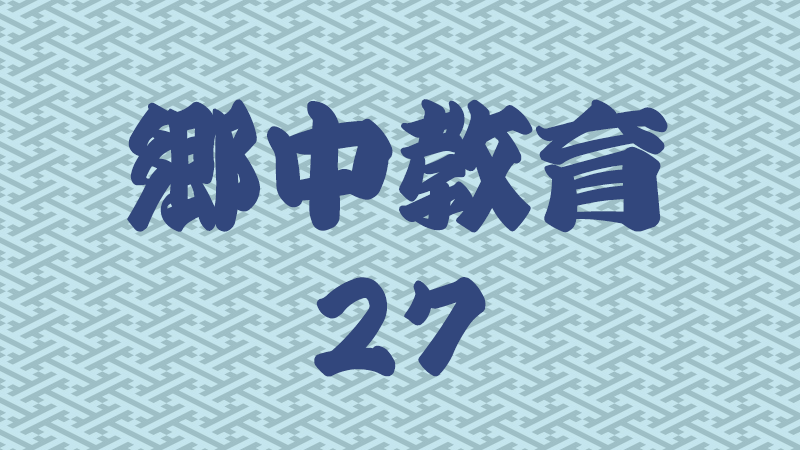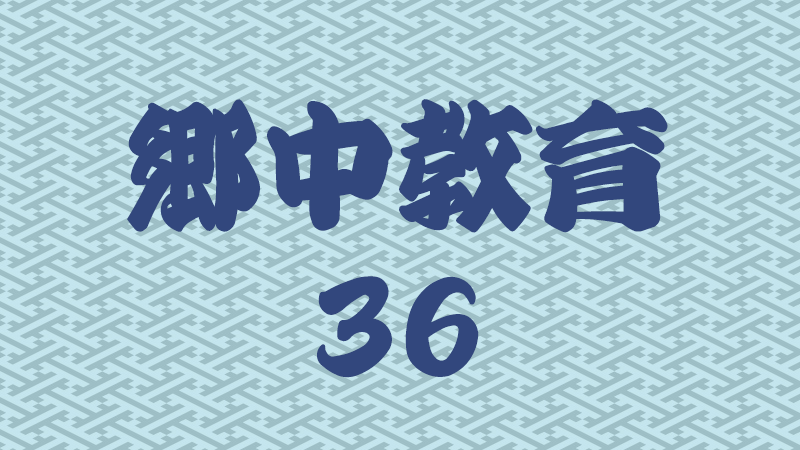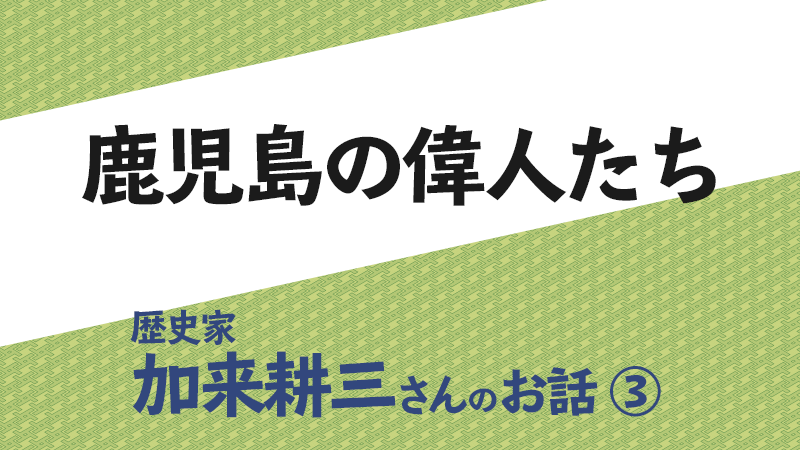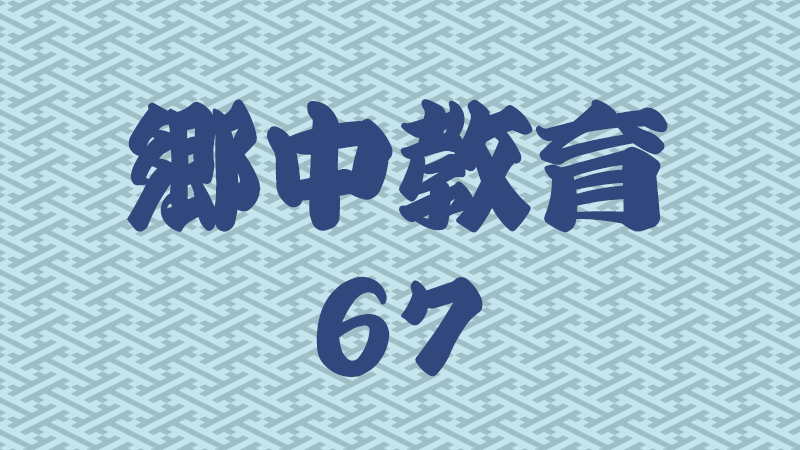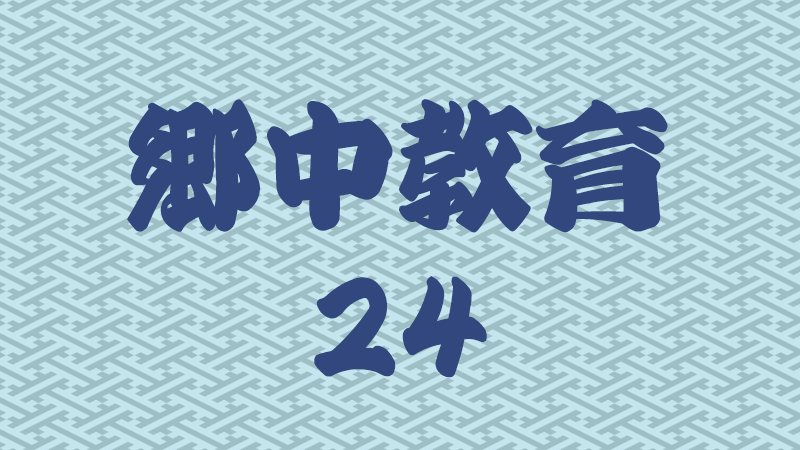今週は、加治木・精矛神社の宮司を務めるかたわら、薩摩武士道の精神を継承する活動に取り組んでおられる加治木島津家 第13代当主・島津義秀さんに、郷中教育の歴史についてお話しいただいています。
昨日は、関ヶ原の戦いで敵中突破を果たした島津義弘公率いる勇敢な兵士のエピソードを語り継ぐ活動が自然発生的に起こってきたというお話を伺いました。
(島津さん)世の中はどうなったかというと、関ヶ原が終わったら戦国時代は終わりだよと徳川は言って、武器を捨てよ、城造りをやめよ、という話になっていきます。
その中で、時の大将であった義弘は、やはり山城にこだわる。なぜならば、いつ攻めてこられるかわからない。だから、常に砦は守りたい、しかし、それは許可されなかった。ということで、この加治木という地に、平城という館のような、隠居所を兼ねた平城を建てる。
しかしながら、人としてのソフト部門はきっちり固めるということで、教育を推奨していくんです。当主自らですね。
江戸時代になってもまだそういうシステムが続いていって、江戸時代はさらにそれがシステマティックになっていって、例えば、朝起きたら剣術の練習をしろとか。
それから江戸時代になると藩校もでき、藩庁もできました。おとなになった(青年が)藩庁に勤めて、帰ってきたらまた後輩たちの面倒を見るとか。そういうサイクルができてきます。
基本的にこの郷中教育のシステムは、二才と呼ばれる人たち、今の高校生くらいの人たちがリーダーになるわけですが、その中から特に徳望の厚い人を選んで、これが二才頭というリーダーになります。たとえば西郷さんがそうです。
二才衆というのがその下の、近い年齢の同僚、1,2歳下の人たち。大久保さんなどがそれに当たります。
それでは、この続きはまた明日。