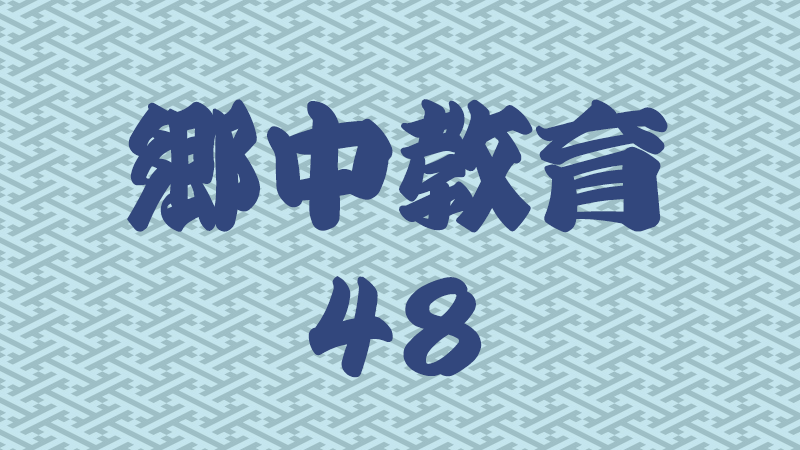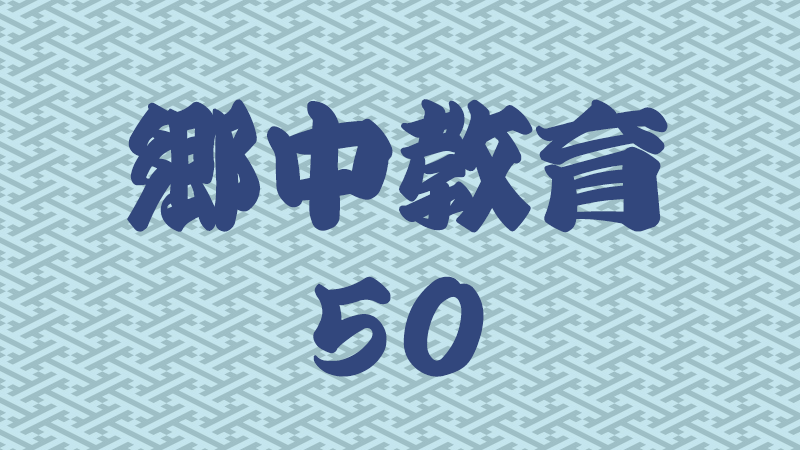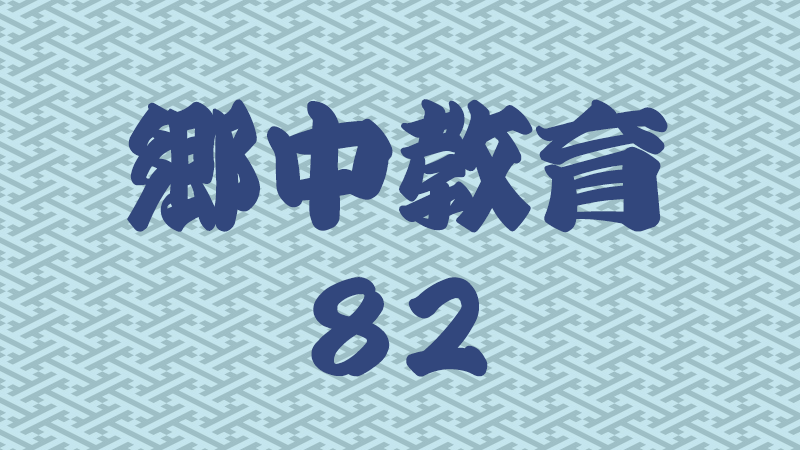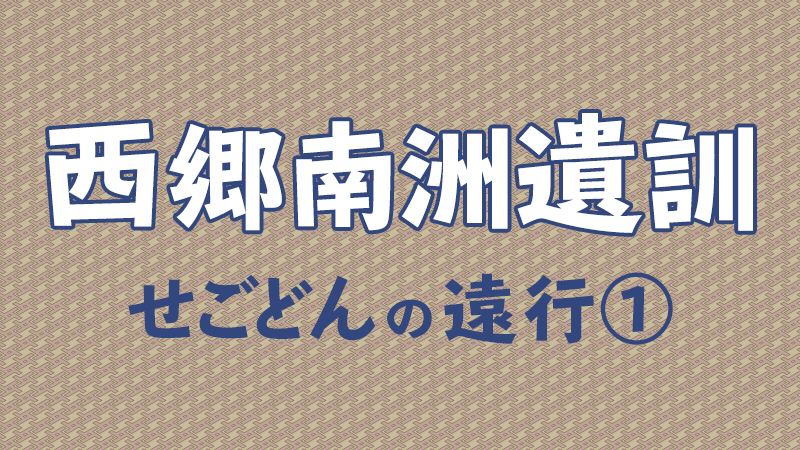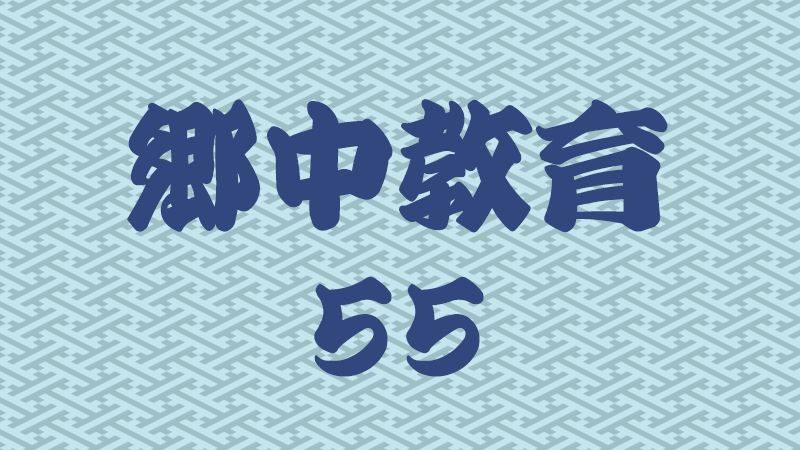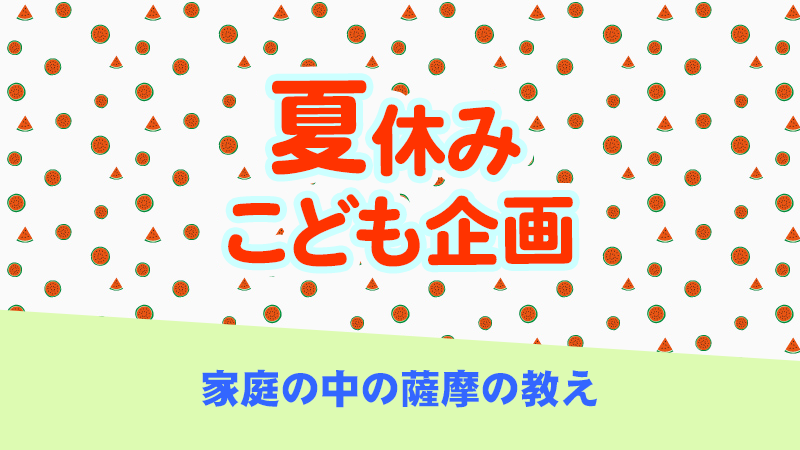今週も薩摩の青少年教育「郷中教育」についてご紹介しています。
郷中の組織は、年齢別に「稚児」、「二才」、「長老」に分けられます。
番組では、郷中の「稚児達の遊び」についてお伝えしていましたが、今朝からしばらくは、武士の家庭に男の子が誕生した時のお話をいたします。
根底にある考え方は、「男児は我が子であっても、我が子ではない。つまり、島津藩の宝」ということでした。
18代藩主 島津義弘の時代。朝鮮の役が起こり、長引く争いに薩摩では、男女の風紀まで乱れるなど大変な社会情勢でした。
それを正す為に作られたのが、「郷中」と言う組織。
そこに住む武士たちは「今日は鍬を取るが、明日は戦いに備え、剣を執る」・・・といった暮らしぶりでした。
そんな武士の家庭に男の子が生まれた・・・となると、それは藩の子供・宝とも言うべき扱いでした。具体的には、こんな様子です。
士族に男児が誕生して一月ほどたつと、両親は、その赤子を連れて鶴丸城へ登城します。
島津義弘公がその子を自分の膝に抱き上げると、お側の者が「この児は、ナニナニの子です」と紹介します。
もし、その父親が戦地で手柄を挙げた武士であれば、義弘公は、その子に
「真、父親に似て、手柄をたてること、父に勝るとも劣らず。忠孝に励み、ご奉仕なされよ」と仰せ聞かせたと伝えられます。
では、今日も、鹿児島のこの言葉でお別れしましょう。また明日。毎日ごわんそ!