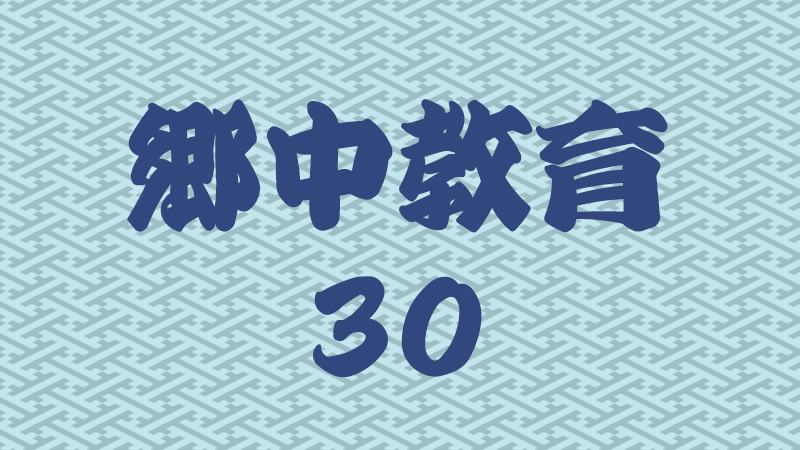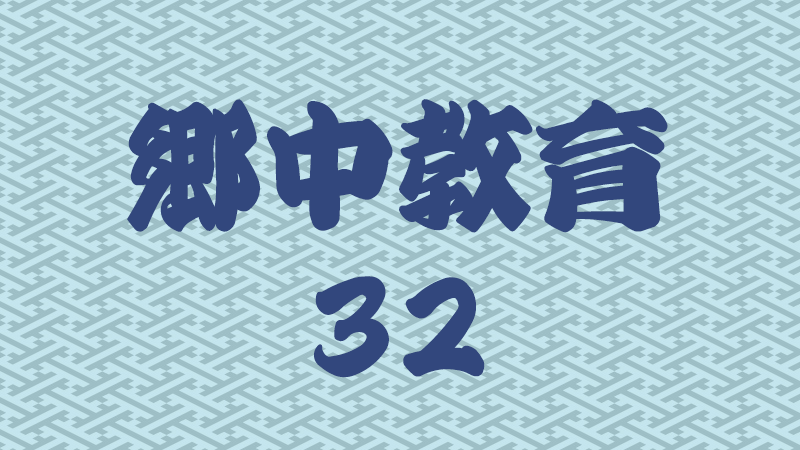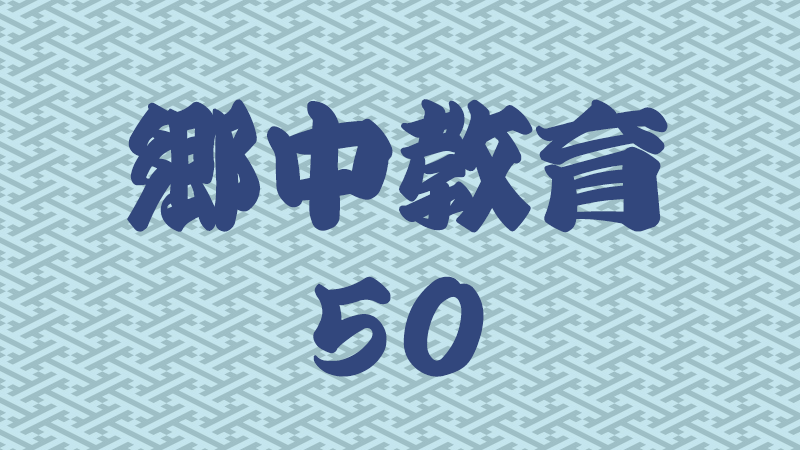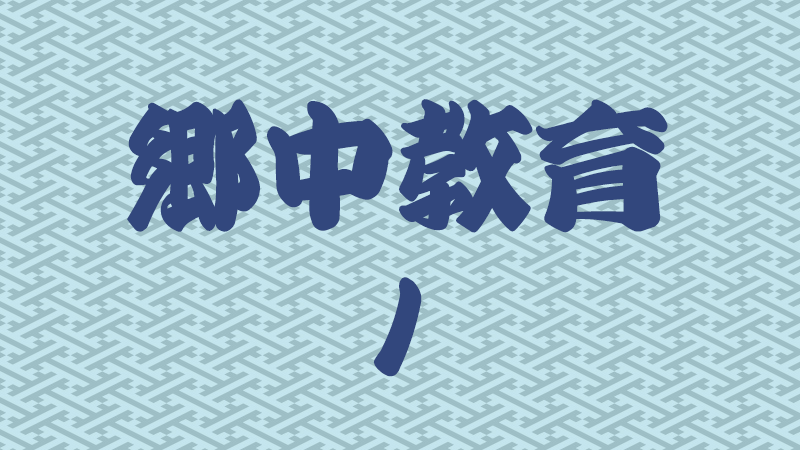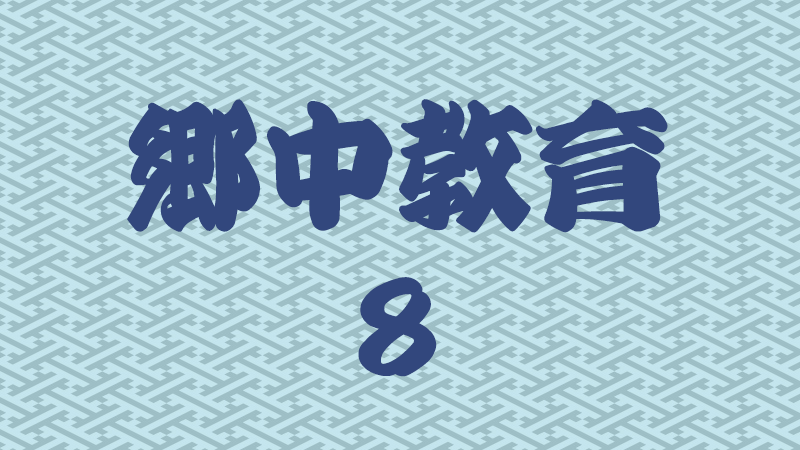今週も薩摩の青少年教育「郷中教育」についてご紹介していきます。
郷中の組織は、年齢別に「小稚児」、「長稚児」、「二才」、「長老」に分けられます。
先週は、その中の小稚児17ヵ条、長稚児8ヵ条の掟をご紹介しました。
この掟は、標準的なものでしたが、方限ごとの例えば「下荒田郷中掟」などを見ると標準的な掟とは、いささか面向きが異なっていました。
これは、その郷中が設けられた地域差から生まれたものだと推測されます。
侍の家庭では、男の子が生まれ7才になると、郷中の組織に入らなければならない掟がありました。
その手続きは、とても簡単で、父親は7才の男の子と一緒に郷中の座元へ向かいます。
「座元」は、各家庭が持ち回りをし、その場所は、毎月変わっていたようです。
郷中の座元へ向かう時、小稚児は短い脇差を差すのがルールだったようで、座元に到着した父子は、まず父親が二才頭に向かって「頼む」と依頼。
二才頭から、二、三の注意事項があった後、稚児の名前を記す・・・
これだけの手続きで全て完了したようです。
次に、稚児の日課です。
朝、目が覚めるとすぐ、郷中の先生の元へ行き、書物を習います。
到着順で授業が行われますが、小稚児が家を出るのを許されるのは、午前8時。
この時間を知らせる鐘、すなわち時鐘は、鶴丸城、現在の鹿児島医療センターの場所にありましたが、今は、鹿児島市易居町、かつての鹿児島税務署隣の「不断光院」に現存しています。
この鐘を基準に鶴丸城下の人々は、一日一日を過ごしていたのです。
機会がありましたら、是非この時鐘をご覧ください。
古の音が聞こえるかもしれませんね。
では、今日も、鹿児島のこの言葉でお別れしましょう。また明日。毎日ごわんそ!