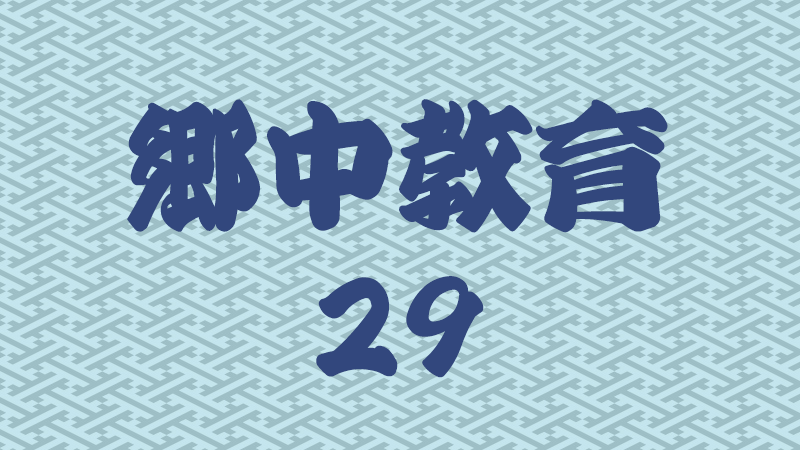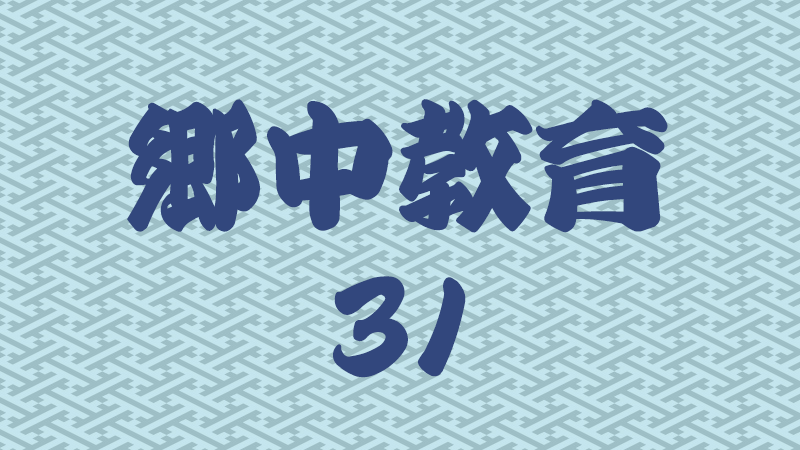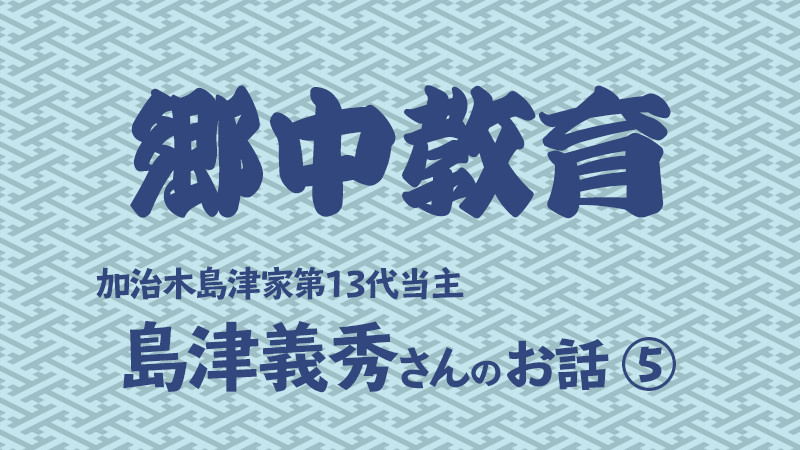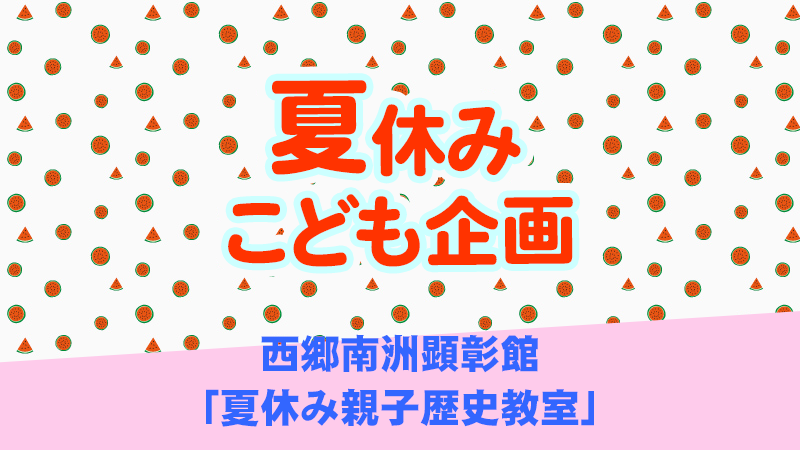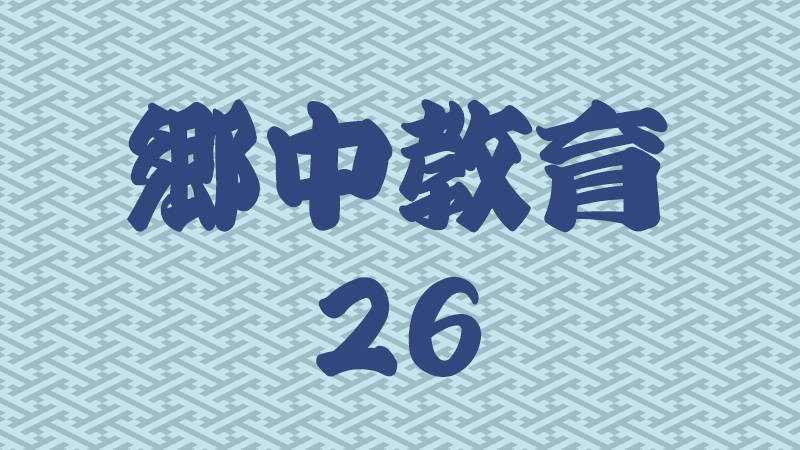今週も薩摩の青少年教育「郷中教育」についてご紹介しています。
郷中の組織は、年齢別に「稚児」、「二才」、「長老」に分けられます。
薩摩では、6・7才から10才までの稚児を「小稚児」、そして、11才になると「長稚児」と呼び、それぞれに掟がありました。
昨日は、幼いほうの小稚児の掟をご紹介しましたので、今朝は、長稚児の掟をご紹介しましょう。
「長稚児の掟」
一、前髪の有る者は、他所の二才又は噺外の二才などに打ち交わる間敷きこと
二、見物などに出る時 はらぐるひ言う間敷きこと
三、児頭より申し渡しの儀 相背く間敷く候、若し又 相背くに於いては 咄しに出間敷く候
など、八ヶ条が年長の長稚児の掟です。
作られたのが宝暦4年10月16日と言いますので、264年も昔のことです。
現代の私たちにも理解しがたい言葉がアチコチに記され、当時11才から14・5才の少年たちが掟を理解し、これを守っていた、と言うのですから驚くばかり。
しかも掟の最後には、「右 此八ヶ条に相背く者は二才頭に申し達す可く候也」と記されています。
この掟に背くことのなかった長稚児が二才組へ進むことが許されるというのですから、現代の私達からすると、とても難しいことに思えます。
では、今日も、鹿児島のこの言葉でお別れしましょう。また来週。毎日ごわんそ!