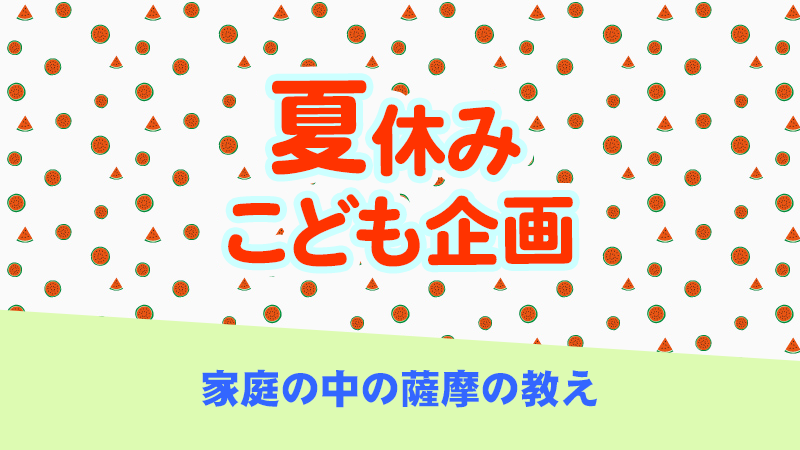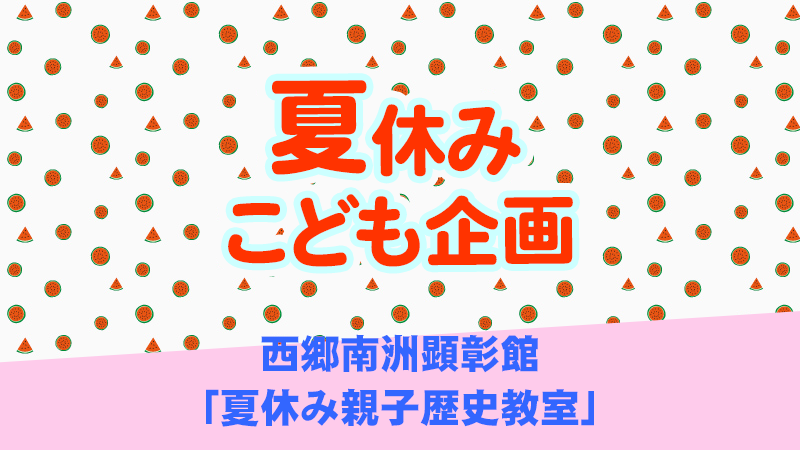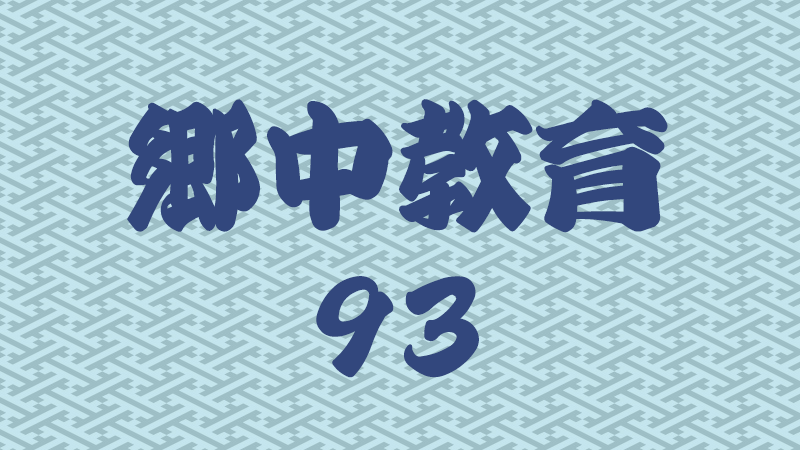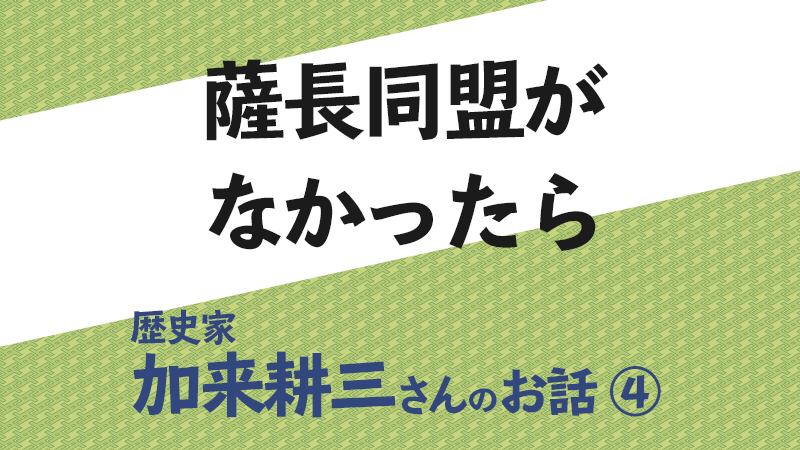9月23日(日)に毎年恒例の「せごどんの遠行」が行われました。
せごどんの遠行は今年で47回目、8キロほどの行程で南洲翁の史跡巡りをするものです。
その生涯と偉業に思いをはせながら、西郷南洲の遺訓を後世に伝えるイベントとして行われています。
およそ2時間から3時間かけて、みなさん、それぞれのペースで歩いていらっしゃいました。お友達と参加される方、あいご会で、親子で、そして3世代でと、幅広い年代の参加があるのも特徴です。
西郷ゆかりの7つの史跡を巡り、スタンプをもらいながら歩きます。
受付であるスタート地は、鹿児島市加治屋町の西郷隆盛誕生地か、鹿児島市武にある西郷屋敷跡です。
ここでスタンプ用紙をもらい、地図通り進みます。スタート地点から甲突川を北上し、護国神社方面から城山へと足を進めます。
最初は「座禅石」へ。西郷や大久保がこの石の上で座禅を組んで修業をしたといわれる石です。
みなさん、石の上に腰かけていらっしゃいましたよ。
次に目指す場所は、草牟田小学校の上にある「夏陰城跡」。
ここは、城山の本営を守るための要所でした。そこが破られたことで、一気に薩軍の情勢が不利になります。今はそのことを想像できないほど静かなたたずまいの場所です。
ボランティアの方が遠行に合わせて下草を刈ってくださったとか。
当日朝6時からの設営など、数多くのボランティアの方が参加されている行事でもあります。
その後も城山を登り続け、城山の頂上へ。城山籠城の本営を置いた「城山本営跡」です。
西郷と仲間たちは、ここでどんなことを思ったのでしょうか?
この後は、城山をだんだんと下ります。西郷さんが寝起きした場所「南洲翁洞窟」。
遠行では、各ポイントには史跡説明ガイドの方もいらっしゃるので、皆さん、熱心に説明に耳を傾けていらっしゃいました。
そして、「晋どん、もうここらでよか」と、別府晋介に介錯を命じた「岩崎谷終焉地」へ。
(さすがに独特の雰囲気で)参加者の方が、手を合わせる姿も見受けられました。
ゴールは「南洲墓地」です。
ここには755基の墓石があり、西南の役に敗れた薩軍2023人が眠っています。わずか14歳で散っていった命もありました。
西郷さんの命日9月24日に合わせて毎年、秋分の日に行われる「せごどんの遠行」。
今年は明治維新150年ということもあり、参加者も多かったようです。
明日からは、せごどんの遠行に参加された方々の声をお送りします。お楽しみに。