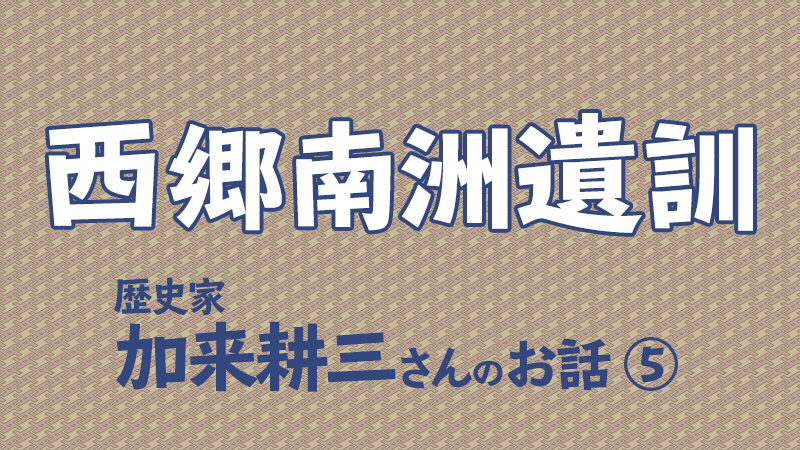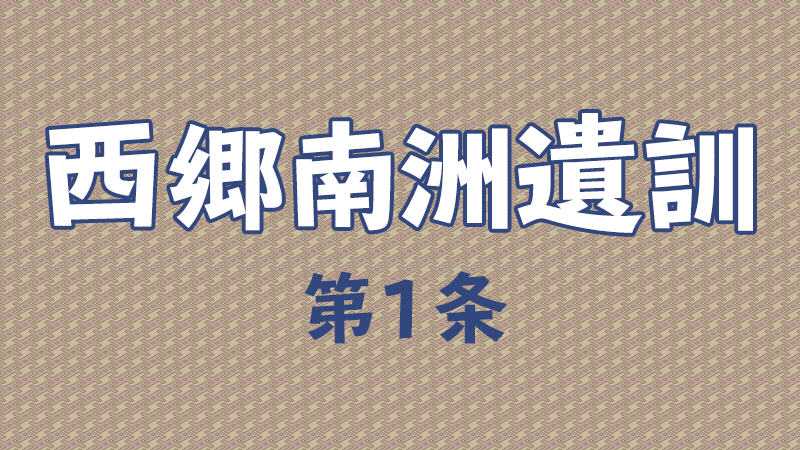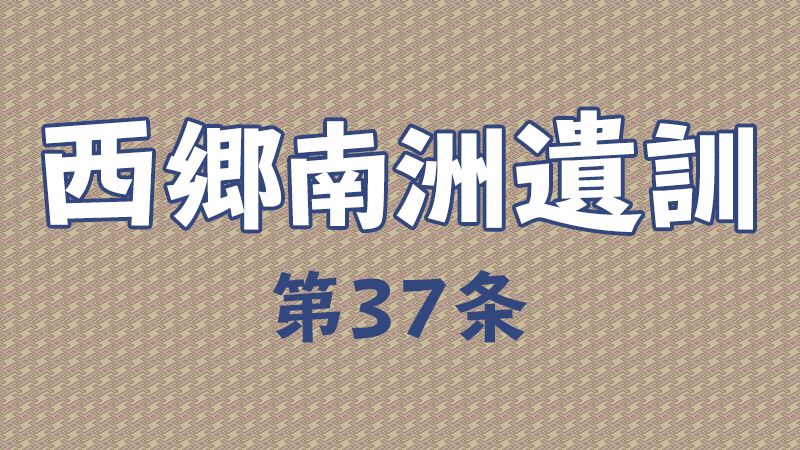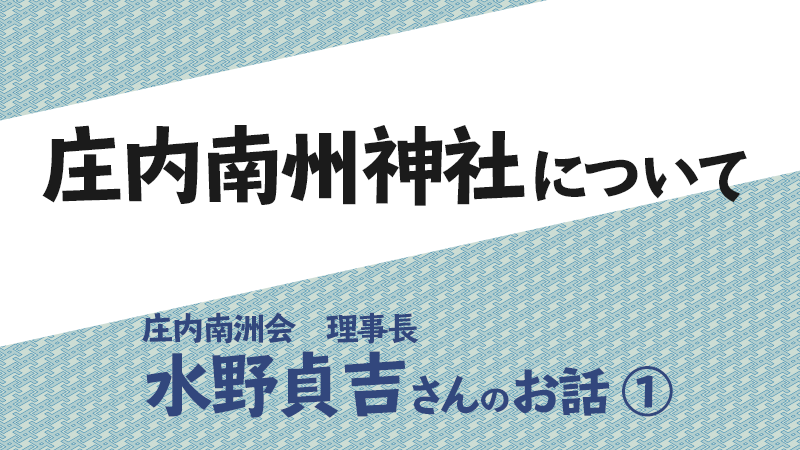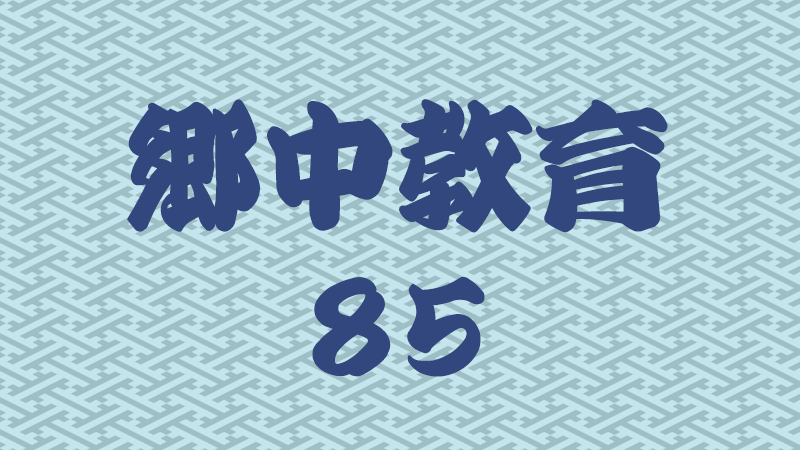明治維新から150年の今年、維新の力を生んだ「薩摩の教え」を、改めて皆さんと共に学んでいるこの番組。1月から日新公のいろは歌、3月半ばからは郷中教育、そして夏休みは、現代の子供たちの中に生きる「薩摩の教え」…とご紹介して来ました。
そして今月、西郷さんの命日9月24日を1週間後に控えた今日からは、「西郷南洲遺訓」に入って行きたいと思います。
先週の歴史家の加来耕三さんのお話にもあったように、旧庄内藩の人々が西郷さんの言葉を聞き取って書き遺してくれた西郷南洲遺訓は、私たちにとっての、ひとつの「薩摩の教え」でもあります。
遺訓の本文が41条、そして追加で2条、さらに問答集などを加えて、全部で53項目からなり、その内容は、人としての倫理から、教育の大切さ、政治や外交にあたっての心構えまで多岐にわたっています。
遺訓にまつわる本は、数多く出版されていますので、お読みになられた方も多くいらっしゃることでしょうね。
原文自体はとても短く簡潔なんですが、昔の文体で書かれており、また、当時の武士の教養であった漢籍や儒教の教えなどがベースになっているため、現代の私たちにとっては、少し(かなり?)むずかしく感じるかもしれません。
また、西郷さんがその言葉を遺した背景、つまり、当時の社会状況、政治や海外の情勢などを知っているか、いないかでは、理解の度合いも随分違ってきます。
そこでこの番組では、南日本新聞社の桑畑正樹さんがお書きになった「西郷南洲遺訓」をもとに、「原文の味わいをそこなわず、可能な限り思想的に片寄りのないリベラルな視点」で訳した現代語で、西郷さんの言葉をお伝えしていきたいと思います。
皆さんのお耳にすんなりとお届けできるよう頑張りますので、ぜひお聞きください!