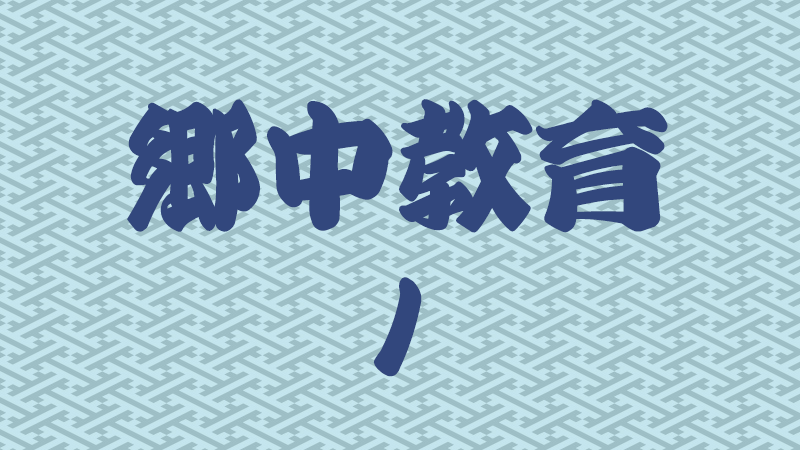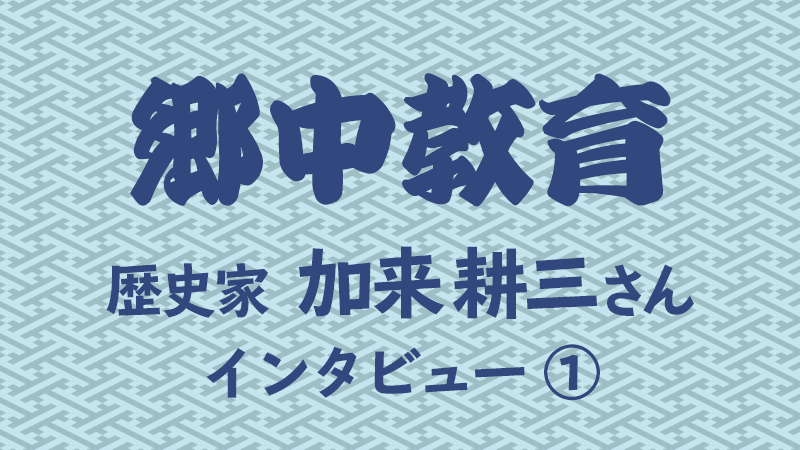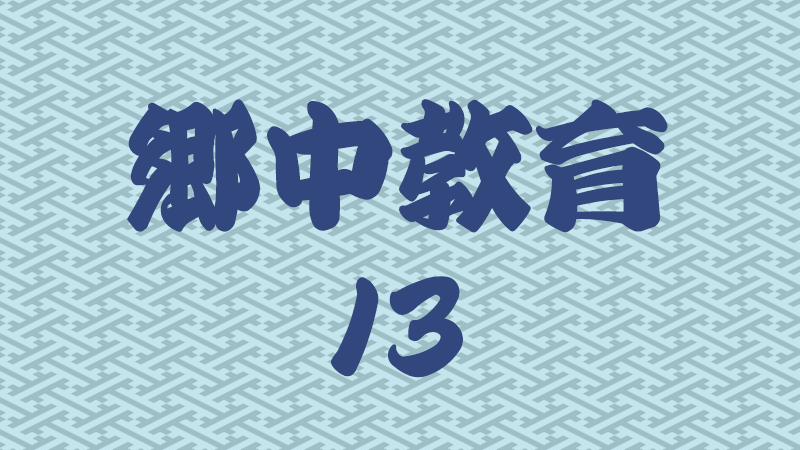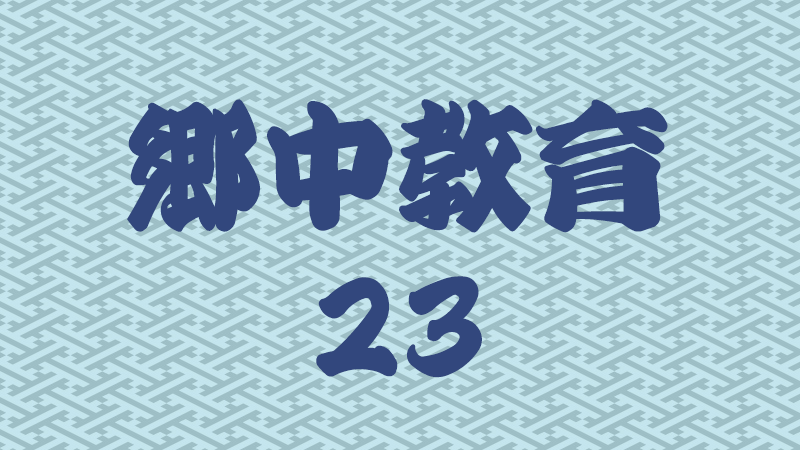今日ご紹介するのは、いろは歌の「ち」です。
まず、言葉の説明から…
- 「知恵」とは、物事の道理を判断し、処理していく心の働きのことを言い、また、物事の筋道をたて、計画し、正しく処理する能力のことです。
- 「能」とは、芸能のこと。
この歌の意味は、
知能は、身につけても荷物にはならない。かえって知能を備えている人を世間の人たちは、敬い、かつ、重んじてくれる。
そして、自分が知能を備えた人に及ばないことを恥ずかしく思うものだ。従って、私たちも知能を磨くことに懸命の努力を尽くすべきだ。
と庶民を諭したのが「ち」の歌なのです。
日新斉の時代の学問は、漢学・儒学。
儒学とは、中国古代の学問で、孔子の唱えた倫理政治規範を体系化し、四書五経を備えています。
四書五経とは、儒教の経書の中で特に重要とされる経典のことです。
そして中国の学問で、日本に4・5世紀ごろに伝来したのが“論語”。
日新斉は、四書五経の四書にあたる論語・孟子・大学・中唐によく目を通し、中でも好んで読んでいたのは、大学。つまり中国の思想書でした。
繰り返し、繰り返し読まれたため、表紙がボロボロになり、三度も表紙を修復したと記録されています。
この歌のように、私たちも知恵をつける努力を惜しまず致しましょう。
それでは、また明日、元気にお会いしましょう。毎日ごわんそ!