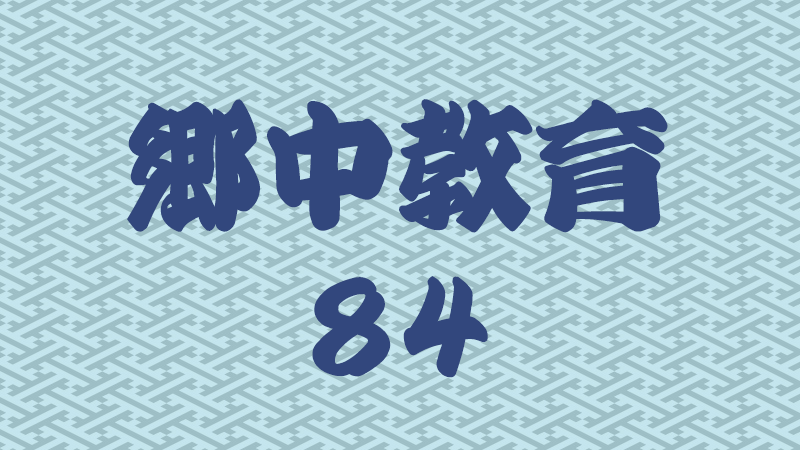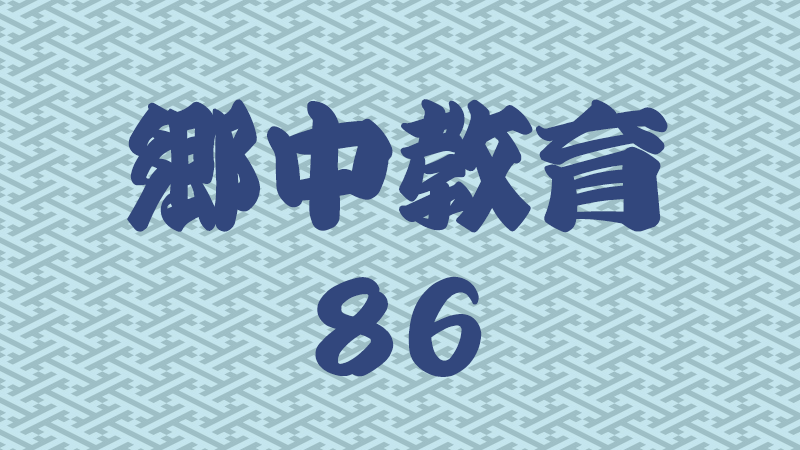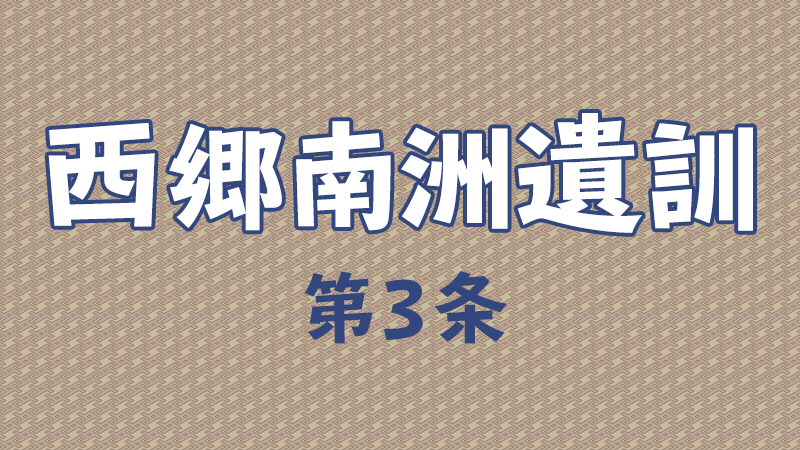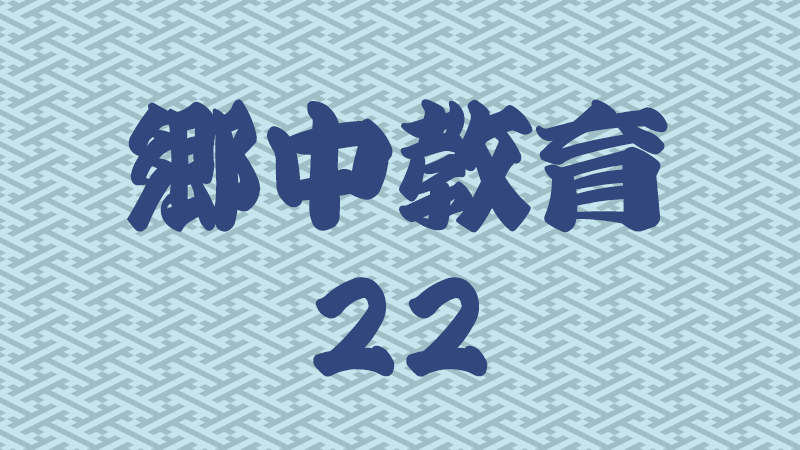明治維新から150年の今年、維新の力を生んだ「薩摩の教え」を改めて皆さんと共に学ぶこの番組。
今週は、郷中教育で行われていた「詮議」についてお伝えしてきました。
「詮議」は、実際に起こる可能性があるけれども、簡単に答えが出ないようなさまざまな状況を設定し、その解決策を郷中の皆で検討するという、いわばグループによるケーススタディでした。
だれもが納得する答えを導きだす若者は皆から一目置かれ、その中でとくに人望の厚い青年が二才頭として郷中の指導に当たったと言われます。下加治屋郷中の名二才頭として慕われたのが西郷さんです。
こうして薩摩の郷中教育では武術、道徳、そして詮議と、「知・徳・体」のバランスがとれた人格形成が行われていたことが窺えます。しかも、青少年が自主的に運営し、主体的に学んでいたというところも郷中教育ならではの特徴といえます。
近い年代の仲間同士で切磋琢磨するからこそ、お互い鍛えられたのです。戦を前提にしているところは現代とは違いますが、机上の勉強だけではない学びを深める上で、見習うべき点が多いように思います。
ちなみに、イギリスで1908年に創設されたボーイスカウトは、薩摩の郷中教育を参考にして生まれたものだと言われています。
400年の歴史を誇る薩摩独特の教育システムは、維新の後も各地で存続していましたが、戦後の思想の変革や高度経済成長の波、少子化の影響などにより徐々に衰退してしまいました。
維新150年の今、郷土で行われていた教育の良さ、見直したいですね。
それでは、今週はこの辺で。