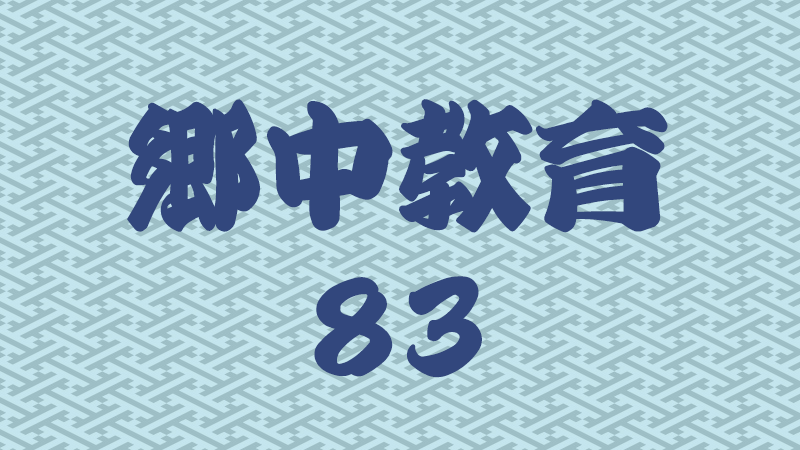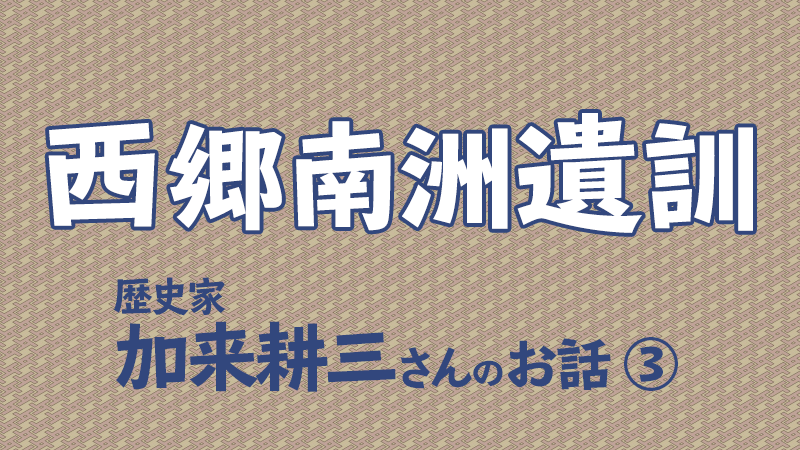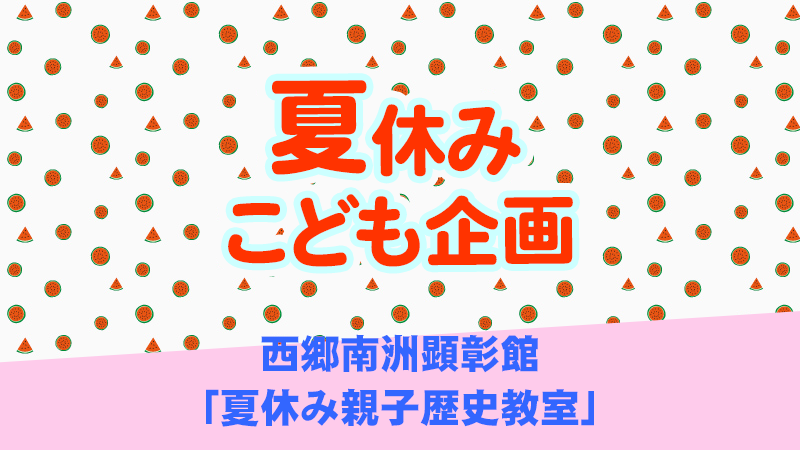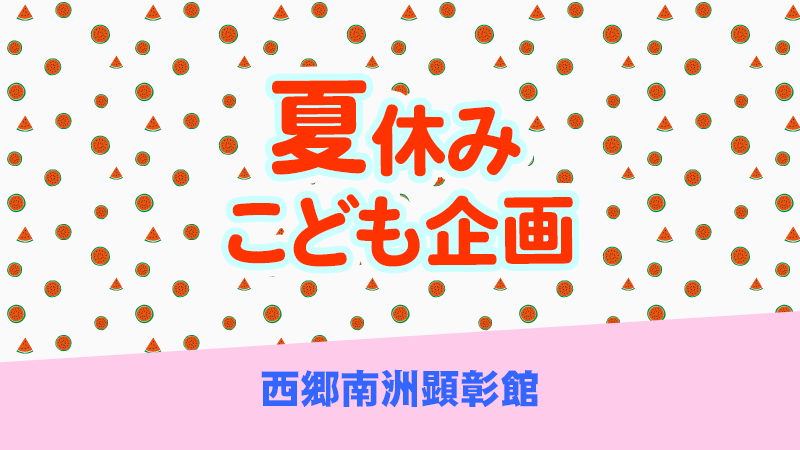明治維新から150年の今年、維新の力を生んだ「薩摩の教え」を改めて皆さんと共に学ぶこの番組。昨日は、郷中教育において若者たちは何を学んでいたのか、加治木・精矛神社の宮司を務めておられる加治木島津家第13代当主・島津義秀さんにお伺いしました。
初期の郷中教育は、関ヶ原の戦いを伝えようという自主的勉強会という性格をもち、その根底には「結束力を高め、一つ旗のもとで薩摩を守る」という、騎士道に通じる精神が流れていたというお話でした。
戦国時代の末期、日新公らによる青少年教育が行われ、士風が養われつつあった薩摩において、関ヶ原の戦いは、まさに一大イベントであったことが想像されます。
敵中突破した島津軍の武勇伝を励みとして「いろは歌」などを暗唱して道徳的規範を身につけ、日々武術に励んでいた薩摩のさむらい。太平の世にありながら、鹿児島には、いまだ戦国時代の気構えが引き継がれていたのですね。
この実践的な薩摩の教育において、もう一つの大事なカリキュラムが「詮議」です。
さまざまな場面を想定し議論しあうことで、瞬時に判断する反射神経を鍛えていたことが、明治維新における薩摩の強みになったというお話は、先月のこの番組の中で、歴史家の加来耕三さんも語っておられましたね。
加治木の郷中教育の中で育った先輩方と共に郷中教育の復活、継承に取り組む島津さんは、現在70代の先輩方が子どもの頃にはまだ、「詮議」による学びが行われていた…ということを教えてくださいました。
小学生や中学生が時事雑誌を読み、一つのテーマについて自分の意見を述べ合い、頭脳を鍛えていたのです。「現在も舎の決め事をするときは、日常的に詮議は当たり前のこと」なのだそうです。
薩摩の子どもたちの知恵と判断力を育んだ「詮議」について、明日もお話を続けてまいります。