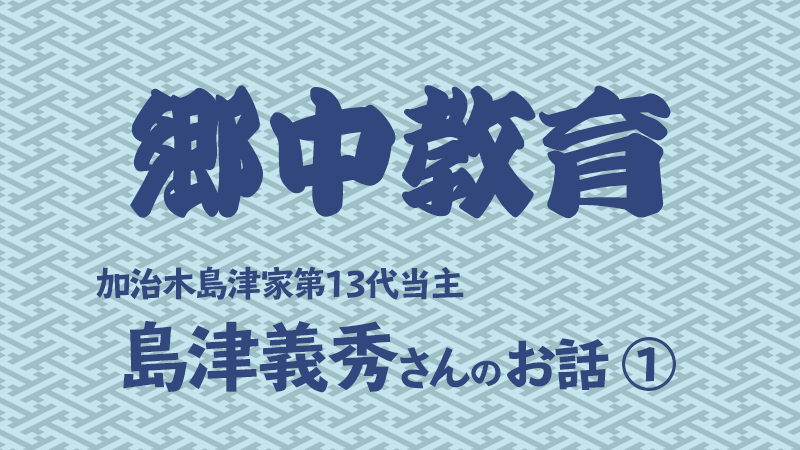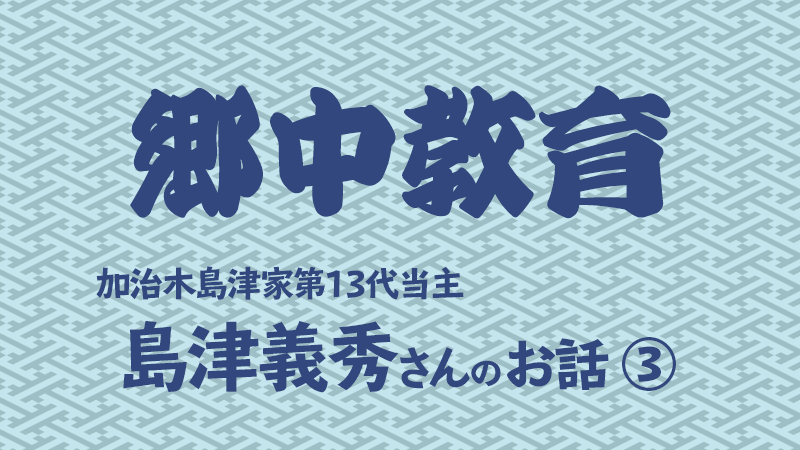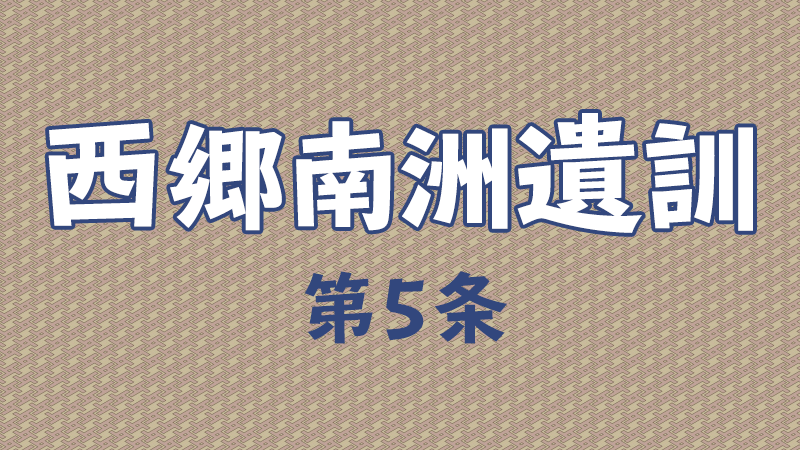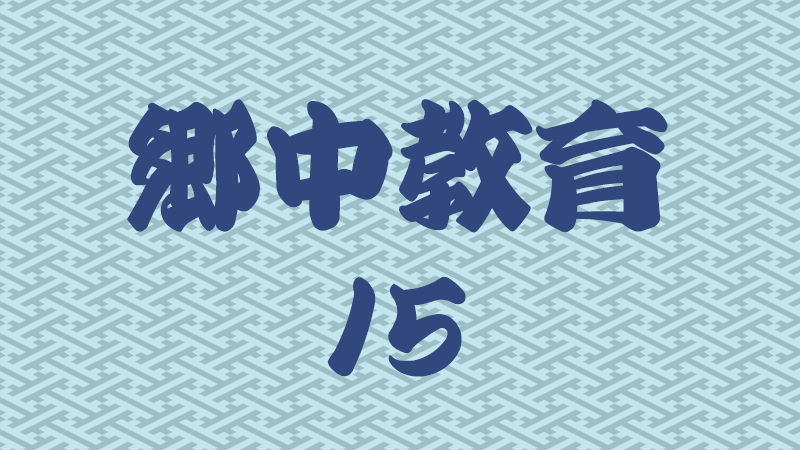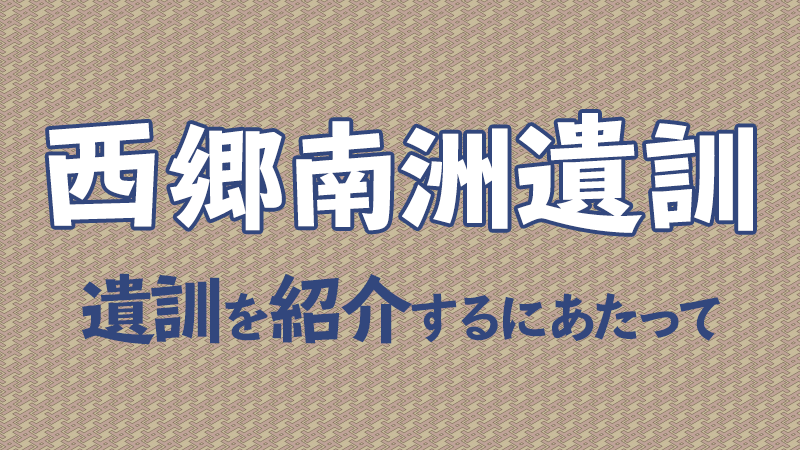今週は、郷中教育の成り立ちについて、加治木・精矛神社の宮司を務めるかたわら、薩摩武士道の精神を継承する活動に取り組んでおられる加治木島津家 第13代当主・島津義秀さんにお話を伺っています。
(島津さん)成立の年代が、確定はされていませんけれども、おおよそ1500年代後半。ちょうど時代としては戦国時代の後期、末期です。当時の薩摩を治めていたのは島津家ですけれども、島津家はまだ混乱期で、豪族たちと戦っている時代です。
例えば、菱刈一族、渋谷一族、肝付一族、そういうもともと地に入っていた豪族たちと、後発で入ってきた島津が戦う。
その島津のリーダーが加世田の領主であった島津忠良、のちに日新斎となられるこの人が、いろいろ戦いをする中で、敵味方なく供養しろとか、あるいは地元に残されている子どもたちへの教えとなる倫理観とか教育指針をまとめ上げていく。これが『いろは歌』ですが、こういったものを作っていくんです。
その『日新斎いろは歌』が、「いろはにほへと」という文字を頭に冠した47首の道徳的和歌。
それを、当時、盲僧といわれる目の見えないお坊さんたちがお経を読むときに使っていた琵琶を改良して、薩摩琵琶というものをプロデュースし、そこに『いろは歌』のエッセンスを盛り込んだものを作詞して流行らせる・・・という仕掛けをしたわけです。
子どもたちの中に広めるということが目的なので、弾き手も聞き手も両方とも子どもたち。若いうちからそういったものが勉強会の中で育まれていった。。。
それでは、この続きはまた明日。