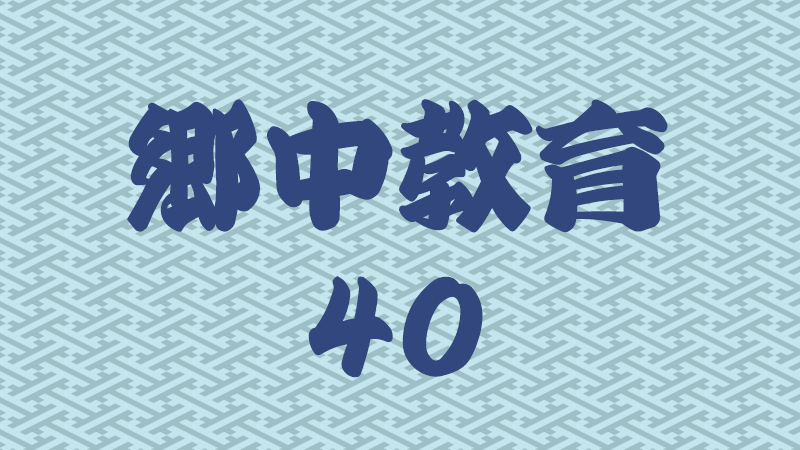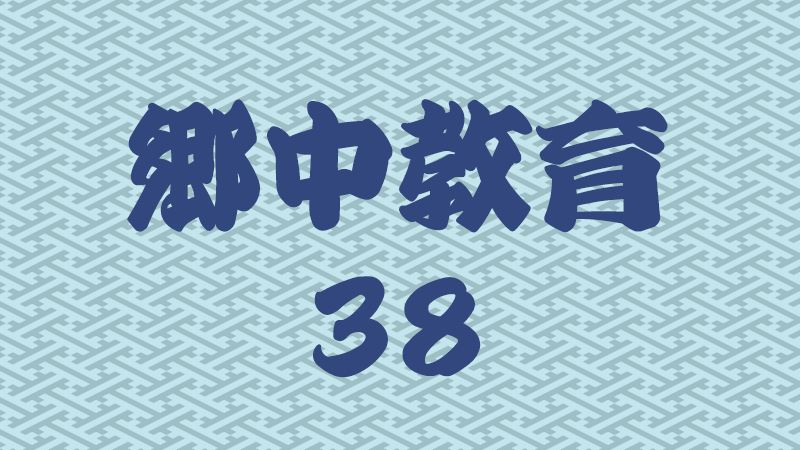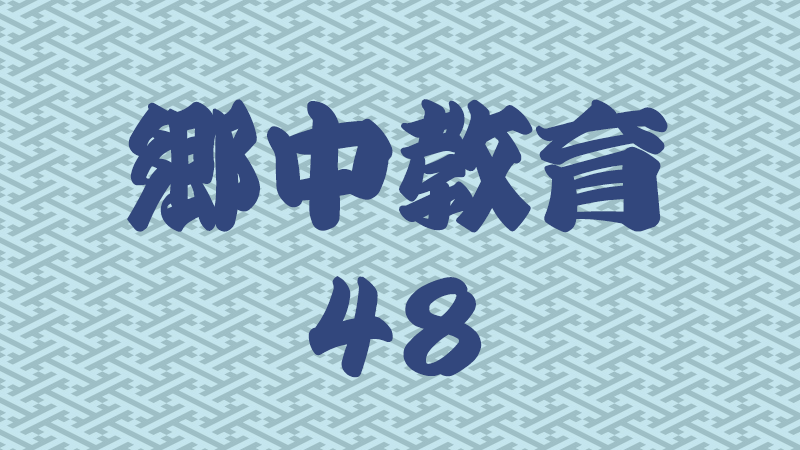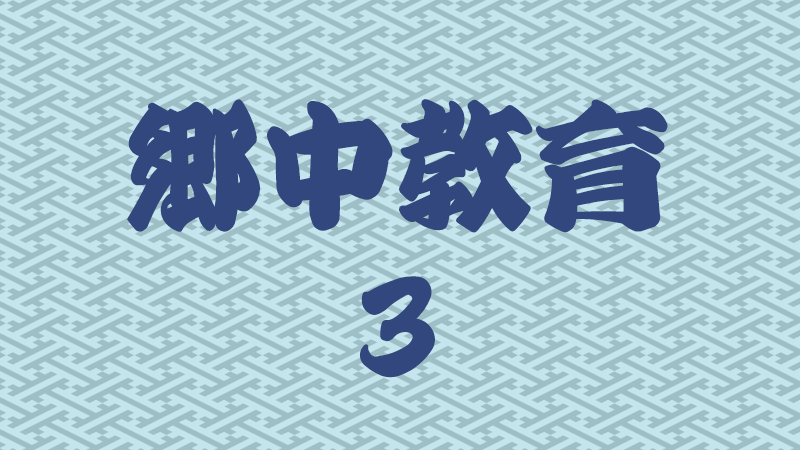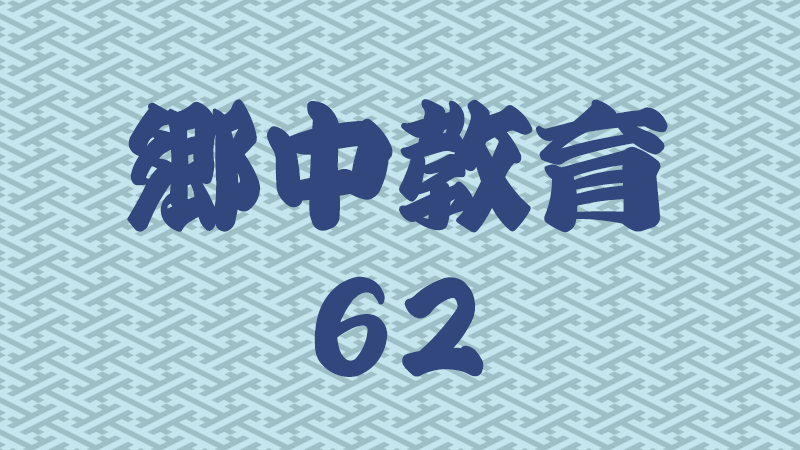今週も薩摩の青少年教育「郷中教育」についてご紹介していきます。
郷中の組織は、年齢別に「小稚児」、「長稚児」、「二才」、「長老」に分けられます。
先週に引き続き、6・7才から10才までの小稚児の遊び「馬追い」をご紹介します。
先週末、鶴丸城下・吉野の原で「馬追い」が催され、その後、現在の鹿児島市立 大龍小学校の前の上ノ馬場で「馬のかけ比べ」、今で言う「競馬」が催されていた・・・というお話をしました。
その名残が、明治時代になっても地方で行われていた「競馬」でした。
明治の世になり、侍や士族たちは仕事を失い生活が苦しくなりましたが、それを救う為、地方では「競馬」が催されていたようです。
その理由は、日本陸軍が必要とする軍馬を飼育し、軍隊に買い上げてもらうことで、少しでも侍達の暮らしに役立てばとの思惑からでした。
現在使われている「地方競馬」という言葉も、この時代から使われていました。
例えば谷山で開催された様子について、古い新聞にこんな記事が残っています。
「谷山郡の郡長婦人が競馬レースに華を添えるため、見物に訪れた。
郡長婦人が馬にまたがって登場、観衆からやんややんやの拍手で迎えられた・・・云々。」
とあります。
郷中教育の稚児たちの遊びが、こんな形で明治につながっていたんですね。
では、今日も、鹿児島のこの言葉でお別れしましょう。また明日。毎日ごわんそ!