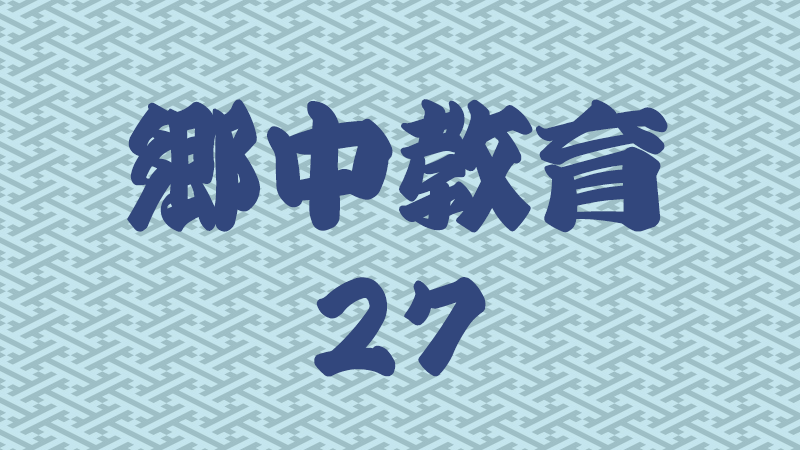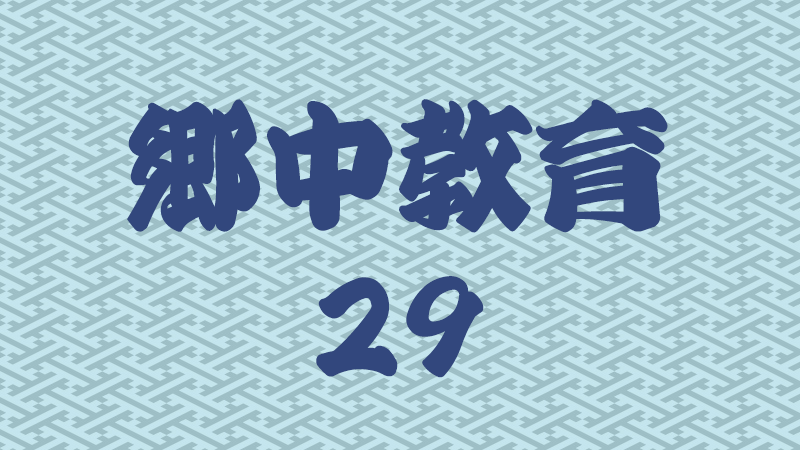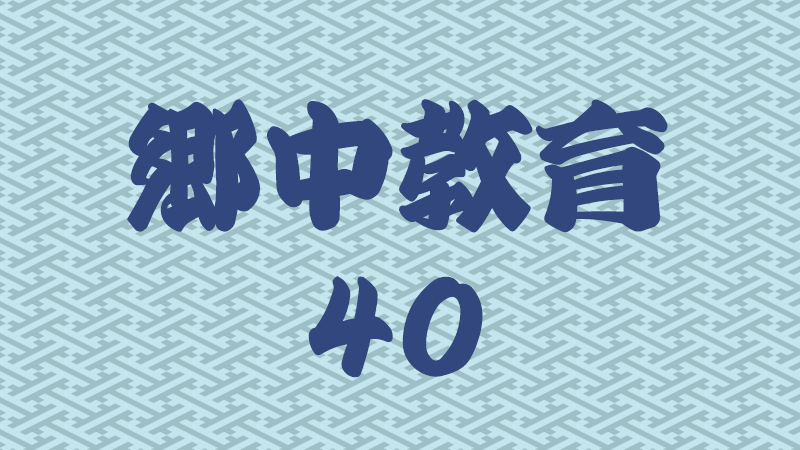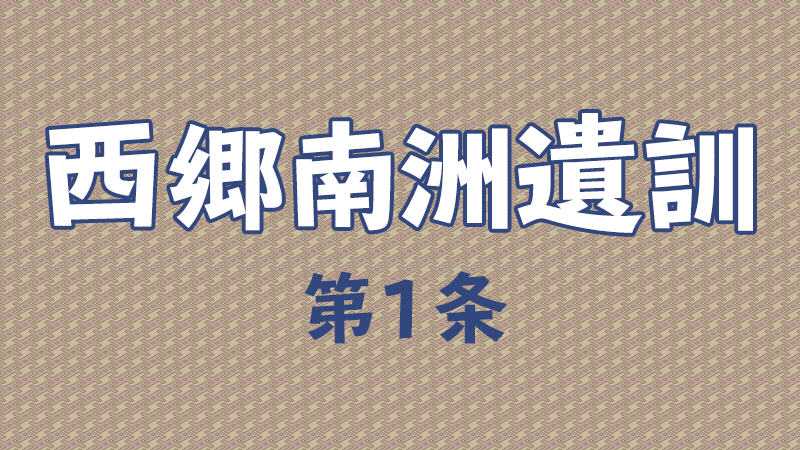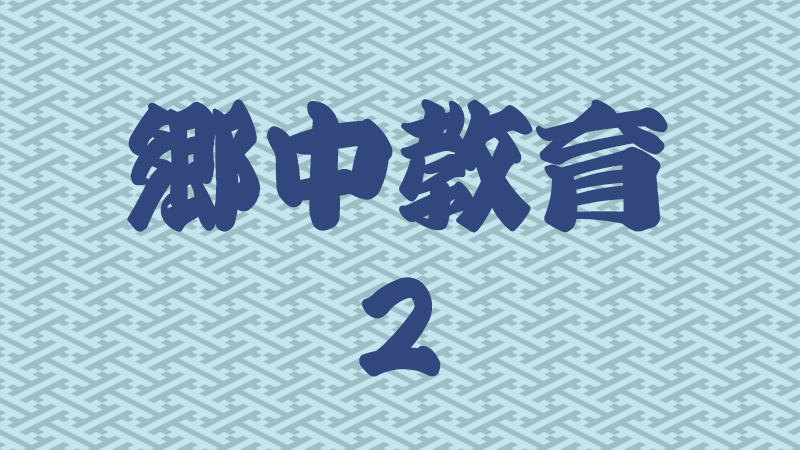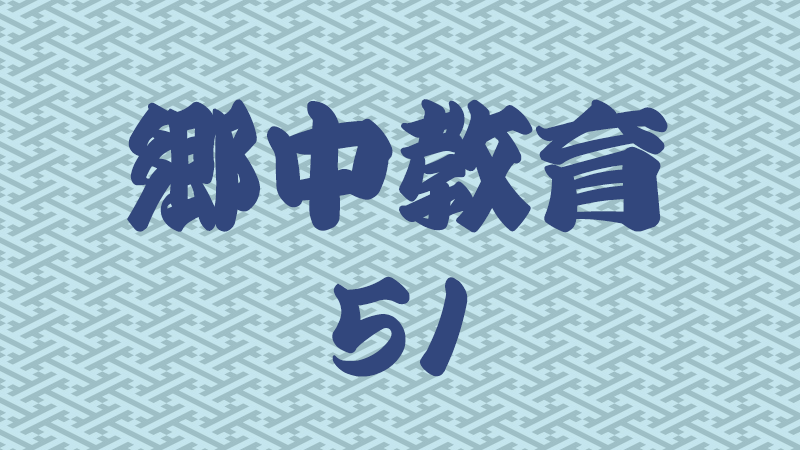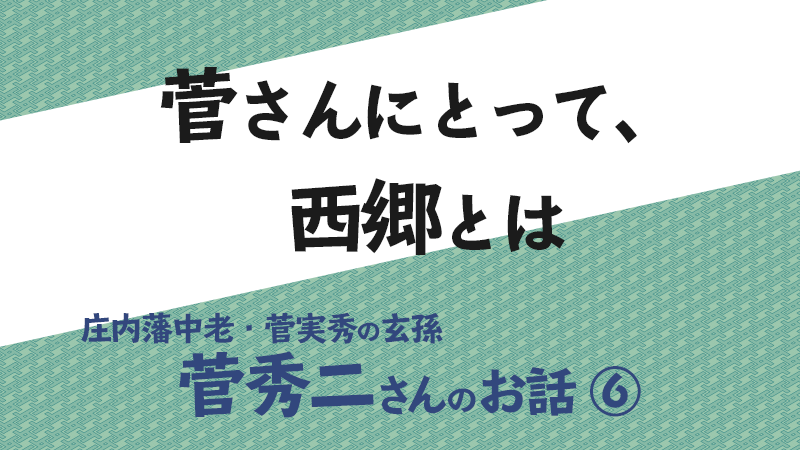今週も薩摩の青少年教育「郷中教育」についてご紹介しています。
今回は、郷中の組織・構成についてお伝えします。
組織は、年齢別になっていて、大きく分けると、「稚児」、「二才」、長老である「長老」の3つに分かれます。
さらに細かく見ると、稚児には、「小稚児」・「長稚児」の二つの区分けがあり、
「小稚児は、6・7才から10才まで」
「長稚児は、11才から14・15才まで」を言います。
その稚児の段階を終えると、
『二才となり、年齢は、15・16才から24・25歳まで』です。
そして、さらに上の「長老は、二才を終えた24・25才以上の二才のこと」で、簡単に区別する手段として、妻帯者のことを長老と呼んでいたようです。
この稚児・二才・長老の区別は、それぞれの方限で少し異なっていたようですが、ここでは、標準的な年齢制限をご紹介しました。
地域によって異なる年齢ですが、さらに稚児の呼び方も方限によって違いました。
例えば、「小稚児・童稚児・ヘゴ山稚児・或いは単純にヘゴ稚児」などがあります。
なぜ、ヘゴ山稚児・ヘゴ稚児と呼んだのでしょうか?
ヘゴとは、シダのことですが、内藤喬 著 『鹿児島民俗植物記』には、
「県下では、大隅南端、薩摩半島枕崎・笠沙などに自生、天然記念物に指定されている」
と記されています。つまりシダ(ヘゴ)が繁っている山に入って遊ぶ稚児たちをヘゴ稚児と呼び習わしていたようです。
このように山に入って身体を鍛える。それを先週もご紹介した「山坂達者」と呼び、郷中教育の掟の一カ条に加えていたと推測されるのです。
では、今日も、鹿児島のこの言葉でお別れしましょう。また明日。毎日ごわんそ!