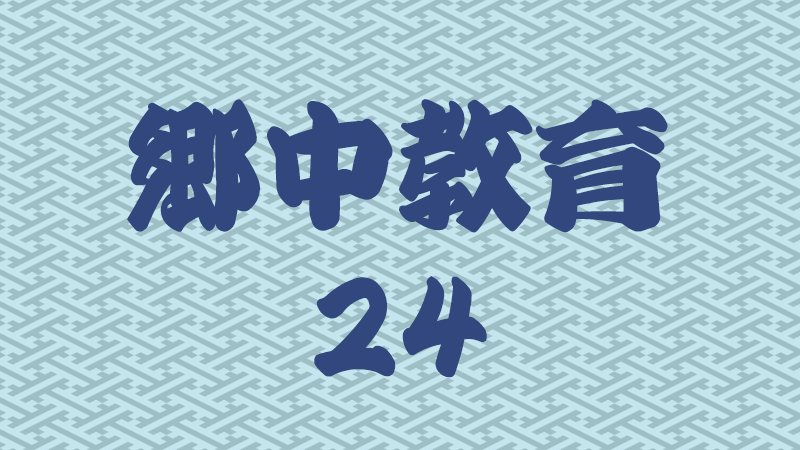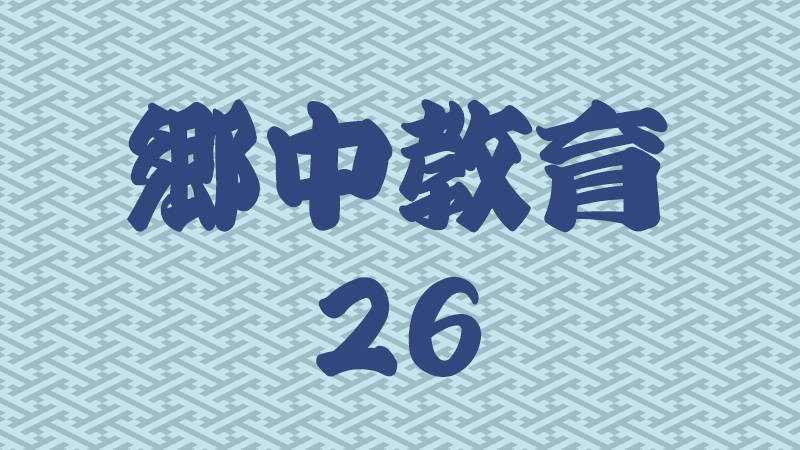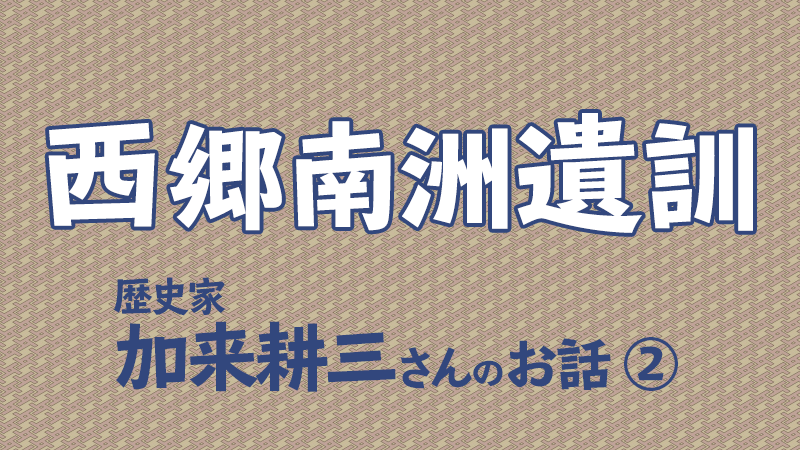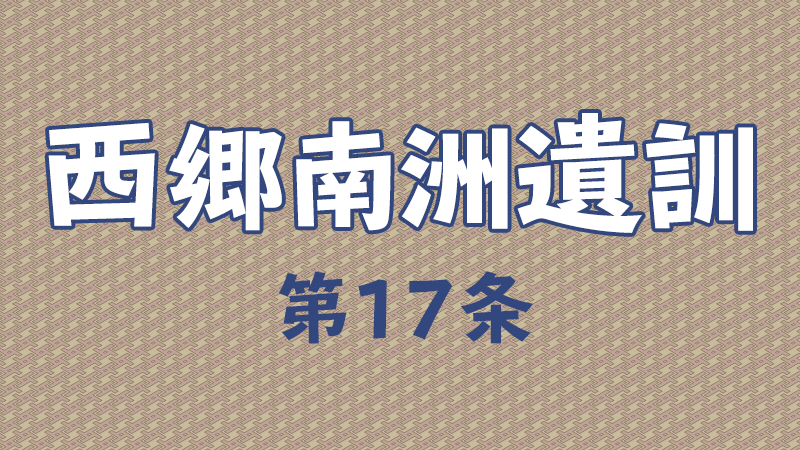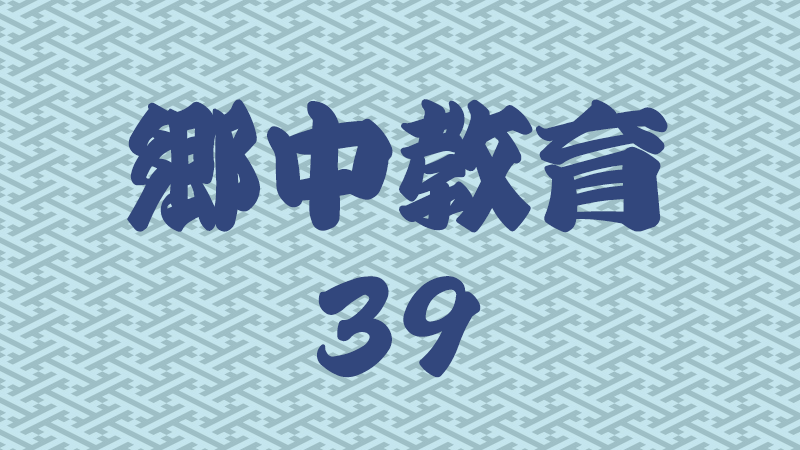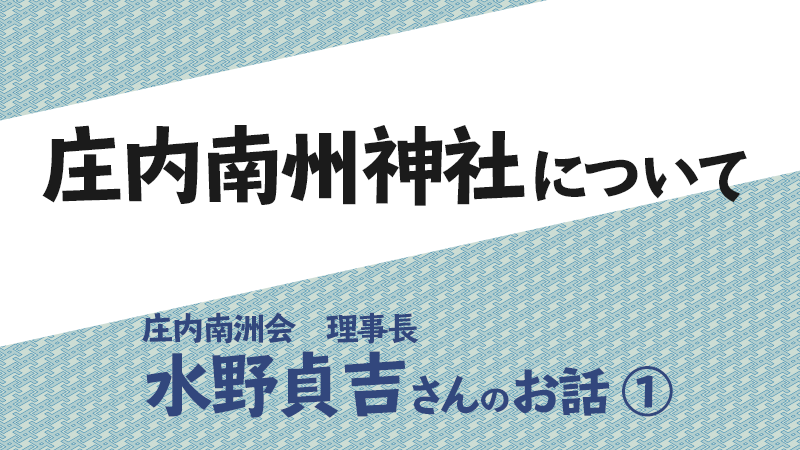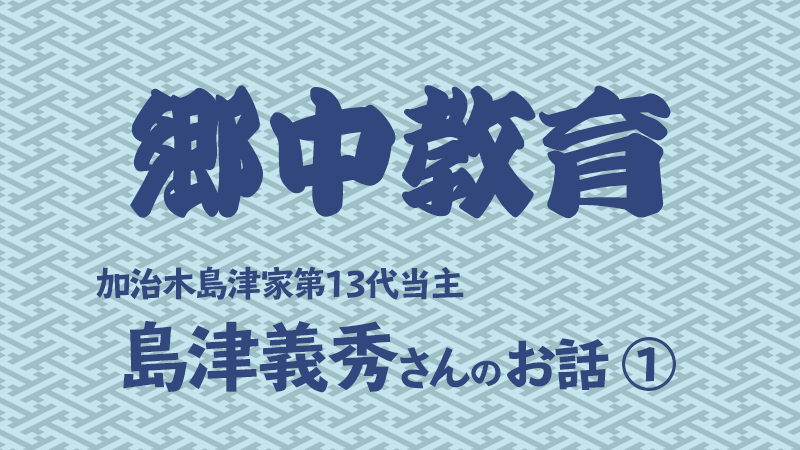今週も薩摩の青少年教育「郷中教育」についてご紹介しています。
先週からお伝えしていますように、薩摩の朝鮮の役出征に伴い、鶴丸城下の風紀は大いに乱れ、留守居役の新納忠元は、心を痛めます。
そこで、自分が少年時代に日新公を中心として催された組織『咄』にならって、新たな組織『二才咄』を作ります。そして忠元は、その組織に属する若侍が日頃守らなければならないルールを『二才咄格式定目』と定めました。
その中で薩摩の諺として、この言葉をご存知でしょうか?
「山坂の達者は心懸くべきこと」
これは、「男子たる者は、険しい山道や坂道も達者に越えられる、たくましい足腰を鍛えておかなければいけない。その為には、普段から身体の訓練をしておき、いざと言う場合に備えておくべきである」
という意味です。
この山坂達者は、現在でも見ることが出来ます。
それは秋、柿の実が紅く色づくころに行われる「妙円寺詣り」です。
慶長5年、関ヶ原の戦いにちなみ、妙円寺跡の徳重神社までのおよそ20キロの道のりを歩いて参拝する伝統行事です。昔は、往復40キロの道のりを鎧・兜に身を固め、夜を徹して歩いていたので、足腰が鍛えられていなければできないことでした。
鹿児島にはこの妙円寺詣りの他に、現在の鹿児島市吉野町の心岳寺詣り、加世田詣りなどの参詣行事がありました。
背景には、神社が建設されている地方の二才衆、つまりその地方の郷中と親睦を深めるという重要な意味があったようです。
詳しくは、それぞれの神社詣りの日にご紹介する予定です。
では、今日も、鹿児島のこの言葉でお別れしましょう。また来週。毎日ごわんそ!