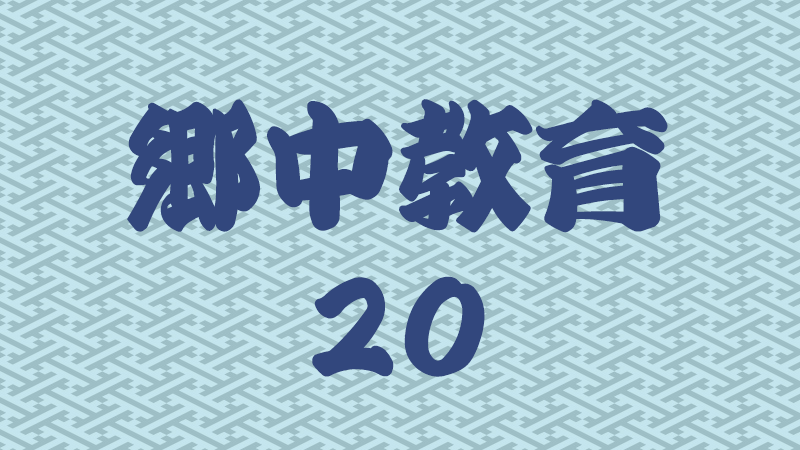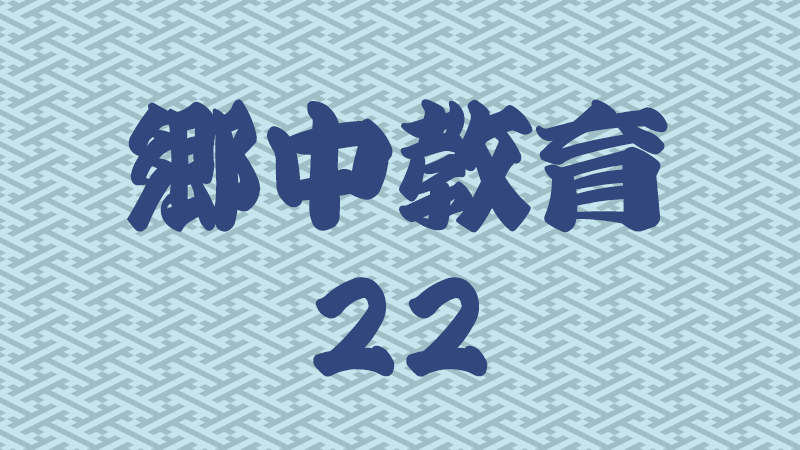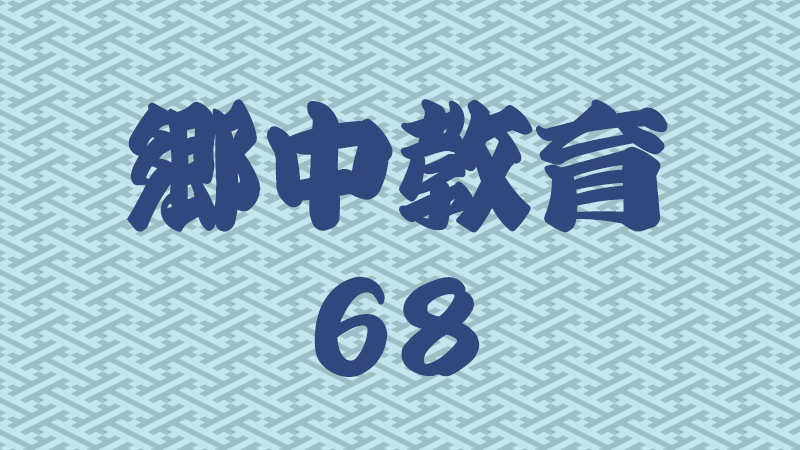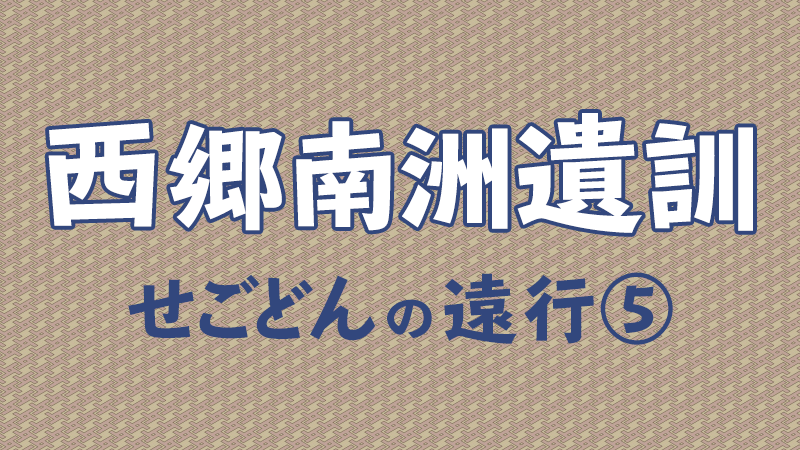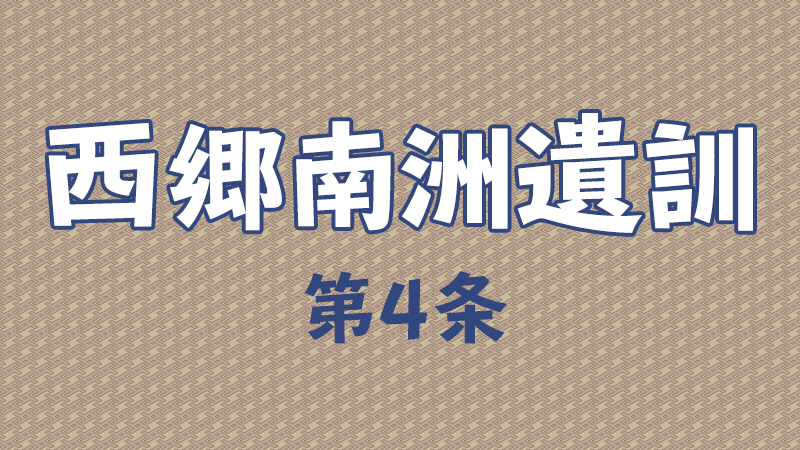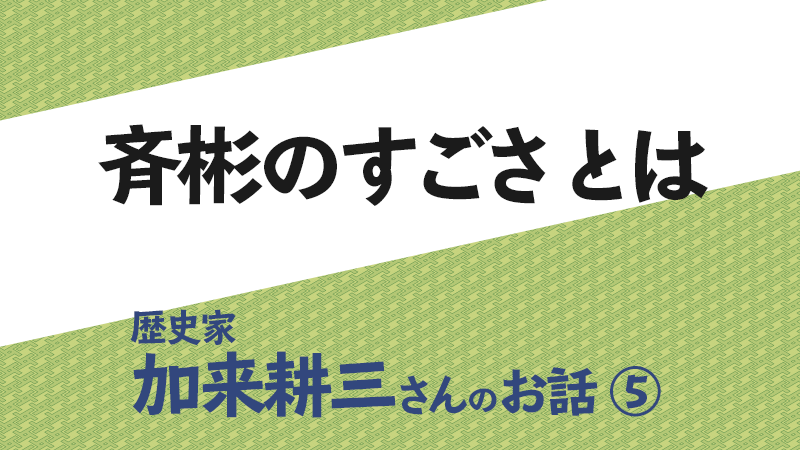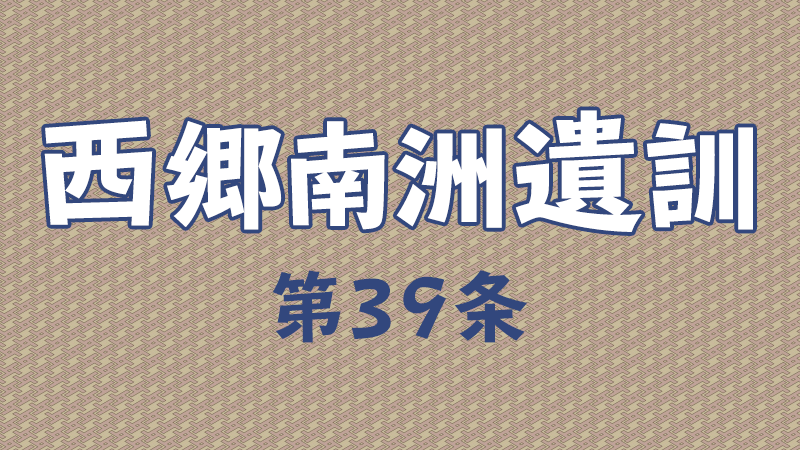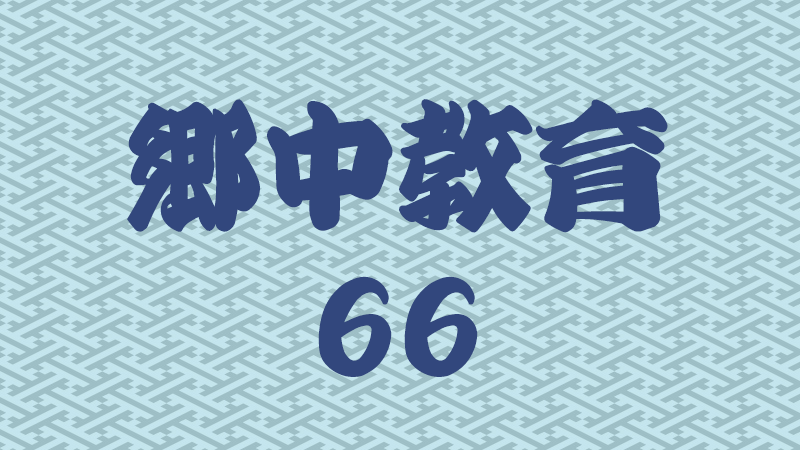今週も薩摩の青少年教育「郷中教育」についてご紹介していきます。
郷中教育の原点は、先月までお伝えしていた、菩薩日新公 即ち 薩摩の戦国武将 島津忠良が人生訓を説いた「いろは歌」にあります。
「いろは歌」は元々「青少年の志操教育」でした。志操教育の「志操」とは、「自分の主義や主張を固く守って変えない心」を言います。
日新公の志操教育を分かりやすく具体化したのが、「いろは歌」でした。
明治維新から300年程前に行われた日新公の「青少年の志操教育」が復活した理由は、豊臣秀吉の二度にわたる朝鮮出兵の影響でした。
夫や息子が朝鮮の戦場へ10年もの長期間出陣したことで、その留守を守っている家族の間に怠惰な空気が蔓延し、風俗が乱れるなど、良くない風潮が流れ出したのです。
例えば、朝鮮の戦場にいる夫や息子から鹿児島の留守中のお宅へ手紙が届くとします。当時は、交通が大変に不便で、手紙が届くこと自体が珍しく嬉しいことでした。
その為、この手紙を招待状の「状」に祝福の「祝」と書いて「状祝」と呼びました。
この「状祝」が届くと、「手紙の主の無事を祝う」ため、人々が集まります。
そして、男性に頼んでこの手紙を読んでもらい、さらに、返事を書いてもらいます。
その後、お礼として酒を交えた宴が行われていたようですが、宴が延々続くうちに、酒の席が乱れ、時には男女の間のよからぬ状況へ堕落してしまう場合もあったようです。
老齢のため、朝鮮へは出陣せず、城の留守警備をする留守居役の新納忠元・樺山善久などは、社会の乱れ、特に青年侍の堕落を大いに嘆き、悲しみました。
このままでは、いけない・・・「何らかの方策を講じなければ」と考え始めるのです。
続きは、また明日。
では、今日も、鹿児島のこの言葉でお別れしましょう。また明日。毎日ごわんそ!