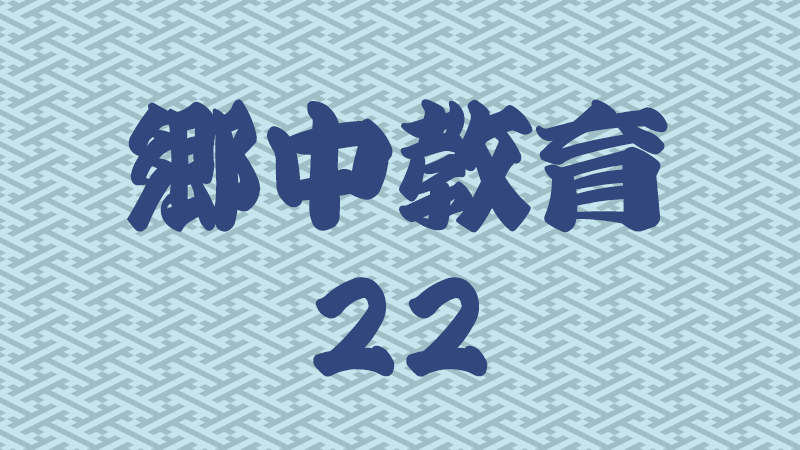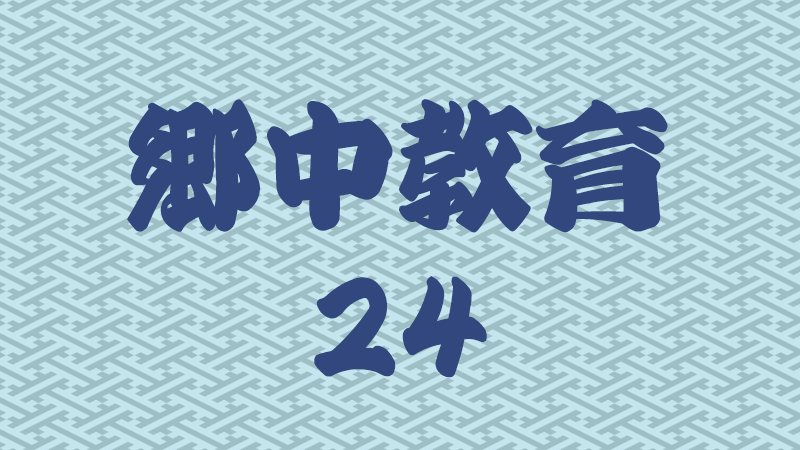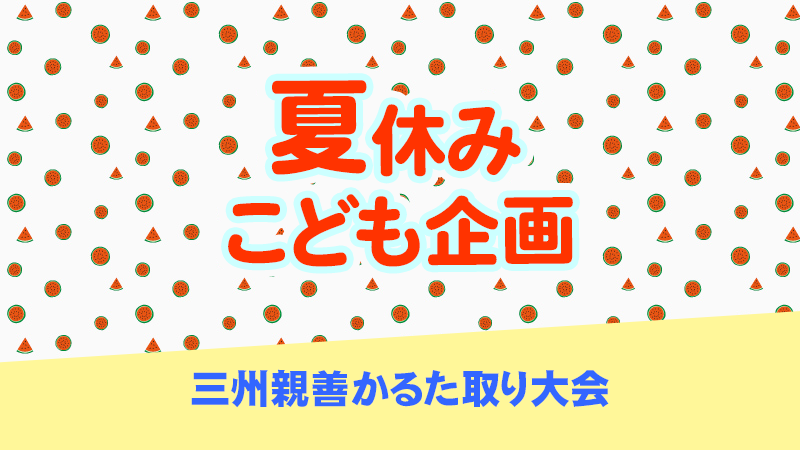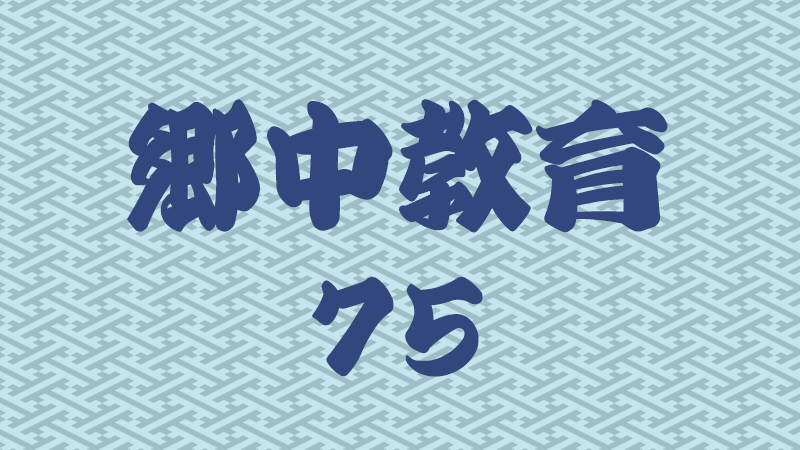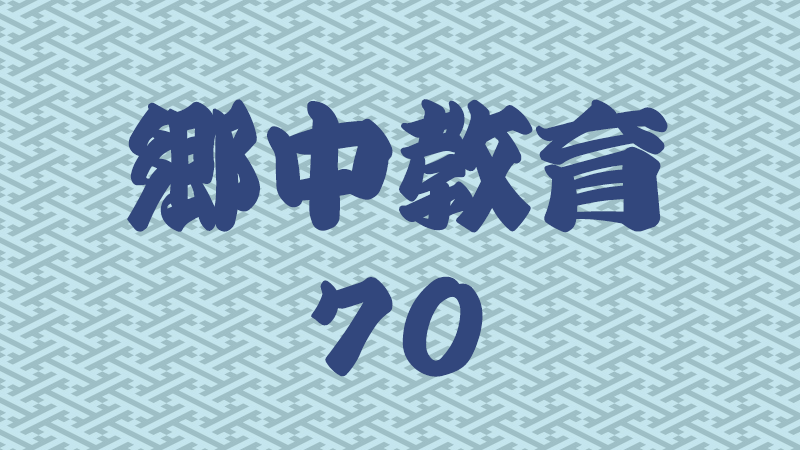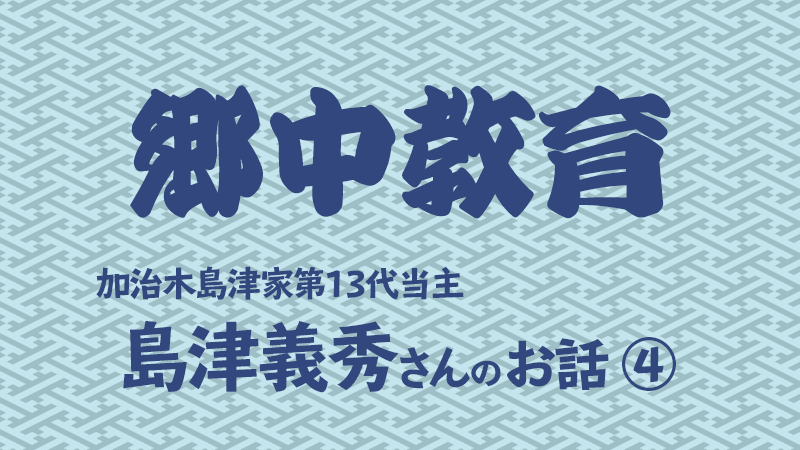今週も薩摩の青少年教育「郷中教育」についてご紹介しています。
薩摩の朝鮮の役出征に伴い、鶴丸城下の風紀が大いに乱れ、これに心痛めた留守番役の新納忠元は、自分が少年時代に日新公を中心として催された『咄』と呼ぶ組織を思い出します。これは、郷中教育の基礎となったものです。
この『咄』を漢字で書くと、「口篇」に「出る」と書きます。
「ハナシ」の他に「トツ」とも読み、意味は『舌打ちすること』です。
「はなし」と読むのは、日本特有の読み方で、この『咄』という字がよく使われているのが、「落語」の世界。
落語家さんが『小咄をひとつ』としゃべる、あの小咄の『咄』のことです。
その意味は、『物事の道理』つまり「人間として行うべき正しい道」を指します。
さて、新納忠元は、城下の風紀を乱さないために、「青少年達の集団」を結成し、そこに集まった、稚児、二才の間で「何でも話し合える組織」をつくり、それを「二才咄」と名づけました。
そして忠元は、「二才咄」に入った若者たちが守らなければならない規約、『二才咄格式定目』も定めます。
この「格式」とは、その人の身分や家柄によって定まっている礼儀や作法を意味し、「定目」とは、「箇条書きにした規則」のこと。
したがって、『二才咄格式定目』とは、「二才咄に入っている青年たちの、家柄によって決まっている礼儀や作法を箇条書きにした規則」のことです。
詳しくは、また明日。
では、今日も、鹿児島のこの言葉でお別れしましょう。また明日。毎日ごわんそ!