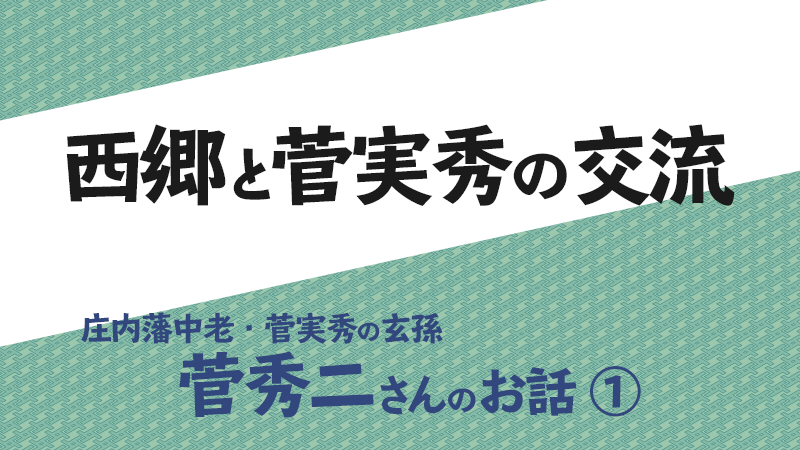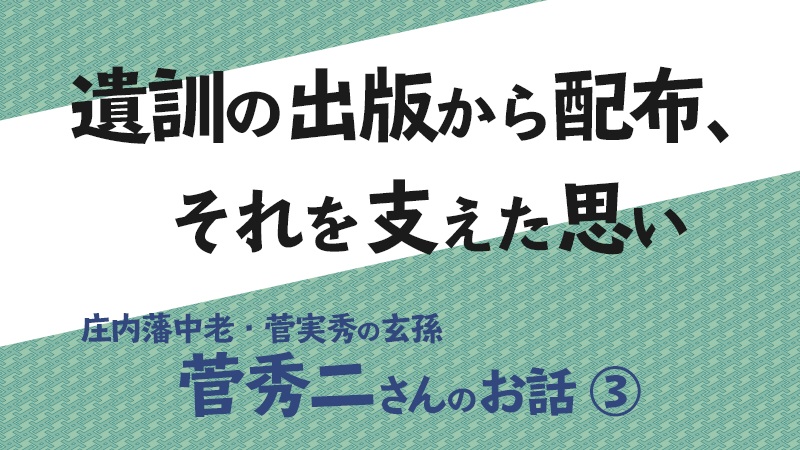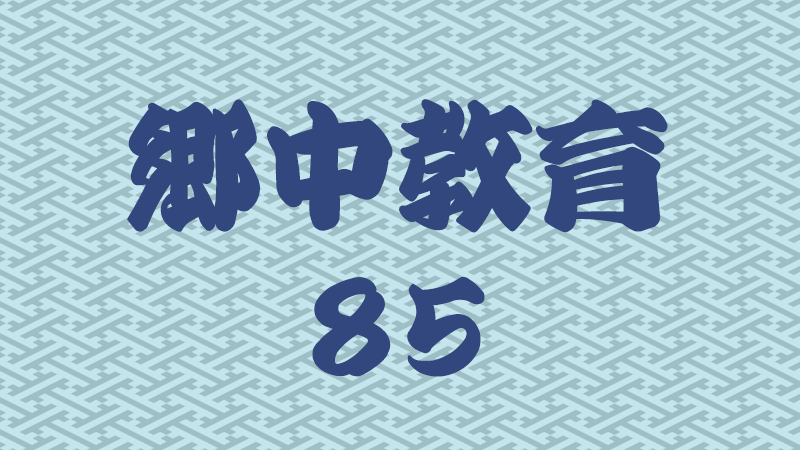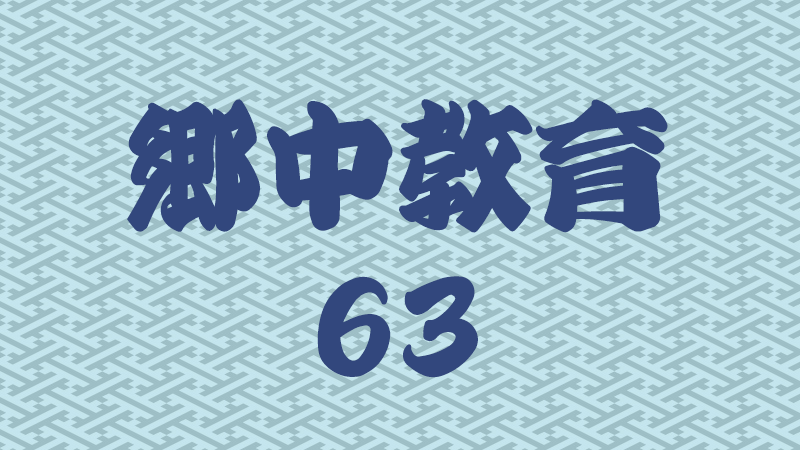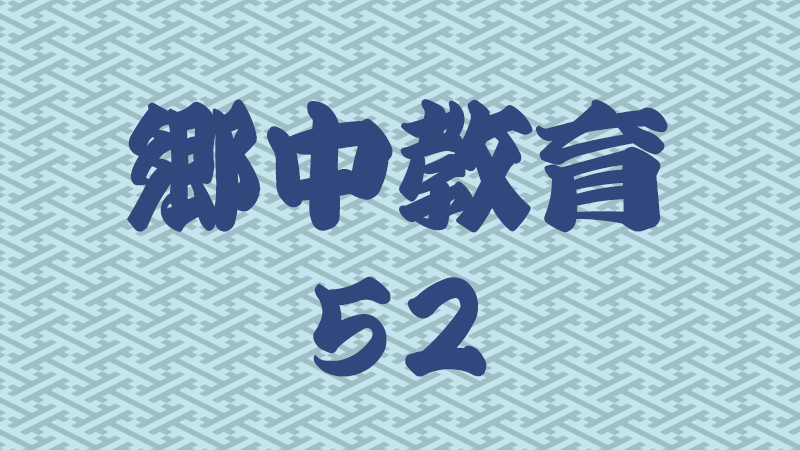今日も庄内藩中老・菅実秀の玄孫、菅秀二さんのお話をお送りします。
昨日は、西郷と菅の徳の交わりとはどのようなものだったかというお話でしたが、今日は、まさに今、菅さんがお住まいの山形県鶴岡市の菅家の屋敷で、西郷南洲遺訓の編纂が行われた当時の様子をお伺いします。。。
(菅さん)「実際作った部屋は12.5畳、隣に控えの部屋5畳と10畳ということで、襖をはずすと全部で28畳くらいの場所に、明治22年の4月から12月にかけて、西郷さんと(生前)直接会って教えをいただいた志士達が集まって、編纂・構成していったと。」
(岩崎)人数としてはどれくらい?
(菅さん)「多い時で20名、普通でも16名くらい。そしてこれは西郷さんからも指摘を受けていることだが、『庄内の人たちは自分(西郷)の話を聞くときに居ずまいを正して(座りなおして)小筆をとって、話している内容をそれなりに要約して書いていた』…と。
『これは致道館(旧庄内藩の藩校)の教えですか?ああいうものの聞き方、尋ねかたをするのですか?』と実秀は西郷から質問を受けたりしている。
(だから)西郷さんも、『いい加減なことは言えないんですよね』というような、実秀と談話の中での話しが残っている。
(全部書き取られてしまうんで)ある面では窮屈だったかもしれませんね…(笑)」
(岩崎)西郷さんも、言葉を選んだかもしれませんね
(菅さん)「その分だけ、西郷さんの心の中にも、いい加減なものを混ぜないで、純粋な部分で教えをしてくれたんだろうと思います」
(岩崎)真剣に言葉を交わしていたんですね…
明日もお楽しみに。